エシカル・シューズデザイナーの勝川永一です。今日は、金澤晋二郎著『「土」の本』をご紹介します。

こちらの書籍は地球の成り立ちから始まり、微生物の活動がいかにして土壌を生み、やがて植物、動物、人類の文明を支えるに至ったかを多角的に解説しています。テーマは、土壌の科学にとどまらず、環境、健康、食、農業、そして未来の宇宙農業まで及んでおり、読む者に「土とは何か」という問いを根本から投げかけています。
著者の金澤晋二郎先生は、土壌微生物学の第一人者で、こちらの書籍はその知見をまとめた渾身の一冊であり、科学と実践、哲学を融合させた「土壌」に関する総合的な教養書です。
金澤先生は1942年北海道生まれ。東京大学、鹿児島大学、九州大学で土壌生化学や土壌微生物学の研究に従事したのち、2016 年に九州大学在任中に金澤バイオ研究所を設立。「農学は実学として役に立ってこそ意味ある」との立場にこだわり、学術的基礎研究の知見を実用技術として活用させるために自ら工場を学内に構えて基礎研究と実用実践の両方を実行してきた人物です。
私は金澤先生とご縁があって、数か月をかけて天然ゴムで作られた H.KATSUKAWA の靴底の微生物による分解実験に先生とそのお子さんの聡子さんとで取り組んでいただきました。
私自身、この数年は環境負荷低減を実現する製品クオリティの開発に勤しんでおります。ファッションシューズのデザインの前提に、環境負荷低減を実現する製品クオリティが必要だと感じ、取り組んでいます。シューズはそもそも合成素材のパーツが多い上に、接着剤なども使用しますので、環境負荷低減を実現する品質の実証はなかなか難しいと感じています。
その中で、天然ゴムのソールであれば合成ゴムと違い最終的に分解するであろうと思い、シューズのサンプリングをしましたが、本当にその天然ゴムは分解するのかという疑問から、こちらの取り組みを行いました。
衣類を微生物で分解するというのは少し唐突と思われますが、先生は食品残渣などの有機物資源はもちろん、竹資材や流木など分解や重金属の不溶化(重合反応)など、さまざまな素材を微生物による分解や重合などを試みてきた実績があります。
2011年に発生した原子力発電所の事故後は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)との共同研究で微生物の分解能力を生かした「土に還る防護服」と分解装置を開発、またコロナ渦では生分解シートで防護服を制作しています。
その活動がきっかけとなり、レザー、毛皮、髪の毛など、現在大量廃棄されているさまざまな素材の廃棄や再利用の相談に乗っています。(※関連リンク「微生物で分解するという可能性、金澤バイオ研究所の研究開発はこちら)
私が依頼したのは天然ゴムで作られたソールの革靴です。約2ヶ月のプレ実験では、結果的に、天然ゴムは分子の結合状態が堅固なために分解に時間を要することがわかりました。このように、今回の実験では、劣化合成ゴムが、じんわり分解して消失するプロセスも予想外でした。次回は、より細かく粉砕して、微生物との接触面を拡大させて再実験を計画しております。
この実験で予想外だったのが、天然ゴムの分解能力の比較をするために同時に実験を試みた、大手スポーツシューズメーカーの合成ゴムでした。合成ゴムは難分解である予想に反して、靴底だけでなく本体の崩壊も天然素材よりもはやく進みました。
そして、私としては、すこし長い目でみて将来的にその分解に適した微生物の発見や、より効率のよい方法を模索するなどして、さらなる実験を試みれたらと思っています。天然素材の靴の劣化が遅いということは、裏を返せばメリットであると思いました。まだ実験はスタート地点ですが、今後も実験を継続できればと思っています。
私自身、改めてこちらの書籍を読むことで、そもそも地球は循環が設計されている事が理解できました。
昨今の社会課題として環境問題があります。それは特に産業革命以降に開発された石油化学の合成科学技術の急激な発展により、深刻な問題として現在の地球環境において分解不能という事実があります。
その人工加工物が一概に悪というわけではなく、それらは人類の発展に役立ってきたことは事実ですが、人口増加と合わせてそれらの量が急増し、自然に悪影響を及ぼしてしまってきているということだと認識しています。
余談ですが、金澤先生はこれまでの研究で難分解とされるダイオキシンや、農薬を分解したデータもお持ちでした。人間が生み出し化学物質も、微生物の力によって分解するというのに驚きました。この本を読むと、企業との共同研究で微生物の力でウイルスも消滅させているというデータもありました。私たちは、自然の力はまだまだ未知の力を持っていると実感いたしました。
200 年前は、自然に対峙しながら人類がどう生きのびるかがが社会課題でしたが、現代の社会課題は以前の社会課題解決によって生み出され自然環境への負担があるものをどう減らすか、またどう生み出さないかであるという事です。その様な視点を私に与えてくれた書籍としては、「地球生命圏」(ジェームズ・ラヴロック 著)もあります。
こちらもぜひ合わせてお読みいただくと、自然界の循環システムといった視野で知見が広がるかと思います。
私としては、自身の納得のいくクオリティで、新たなシューズをデザインしたいと考えています。この数年間は模索の連続です。
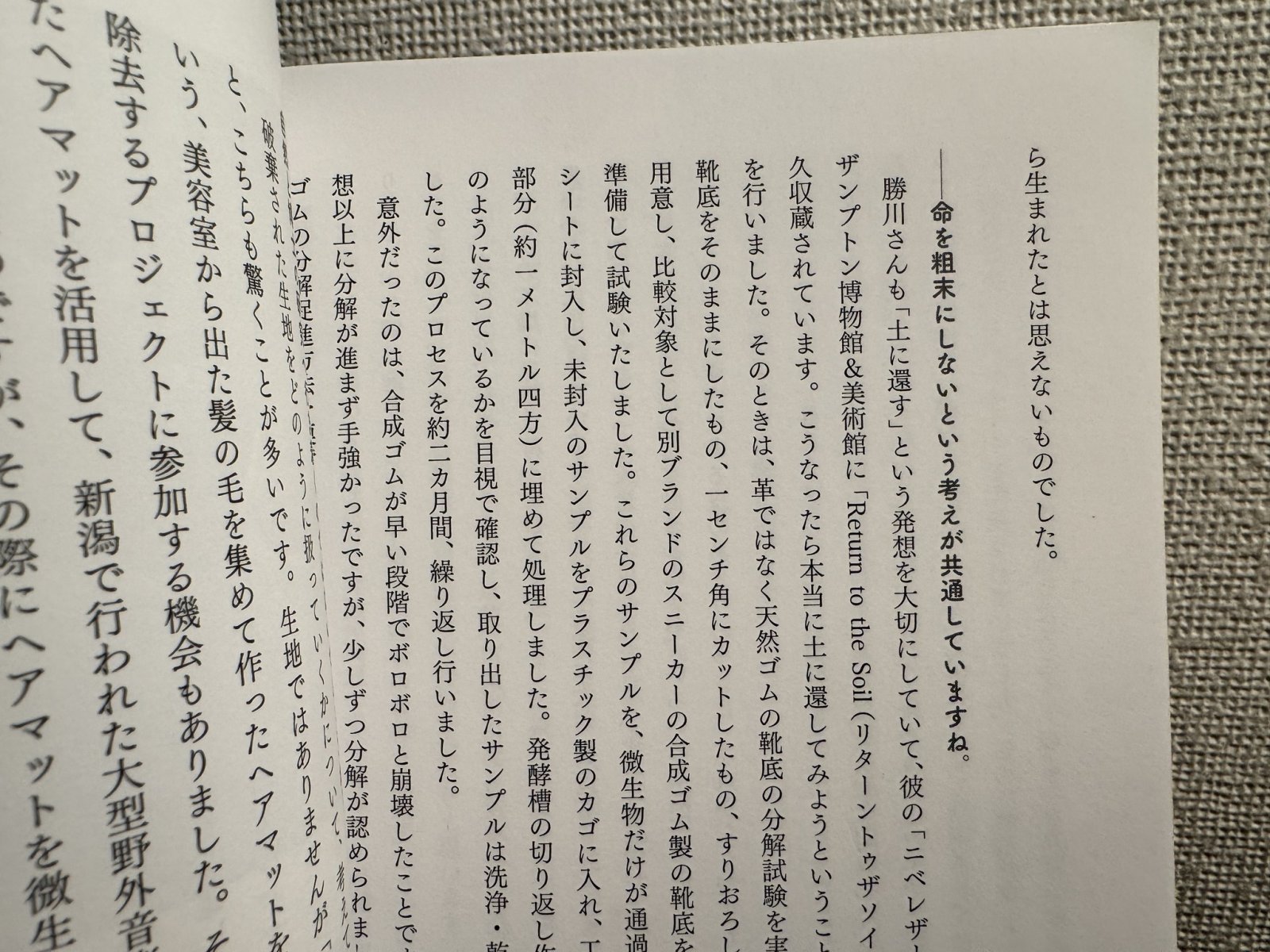

 実験のため、ソールを土に埋める作業
実験のため、ソールを土に埋める作業 実験中のソール(比較対象とし大手スポーツメーカーのソール)
実験中のソール(比較対象とし大手スポーツメーカーのソール)

エシカル・シューズデザイナー
大学卒業後に国内靴メーカーを経て渡英し、英国ノーザンプトンのトレシャム・インスティチュートで靴づくりを学び、PAUL HARNDENに師事。2007年、修理職人として働きながら自身のブランドH.KATSUAKWAを設立、国内外の主要セレクトショップで展開。また著名ブランドとのコラボレーションも多数手がける。2010年に靴修理店「The Shoe of Life」を開業し、累計6万足以上を修理。2016年、作品「Return to the soil」が英国ノーザンプトン美術館に永久収蔵。2024年、国内靴ブランドとして初のB Corp認証を取得し、靴を起点にエシカルで持続可能なデザインを探求している。
大学卒業後に国内靴メーカーを経て渡英し、英国ノーザンプトンのトレシャム・インスティチュートで靴づくりを学び、PAUL HARNDENに師事。2007年、修理職人として働きながら自身のブランドH.KATSUAKWAを設立、国内外の主要セレクトショップで展開。また著名ブランドとのコラボレーションも多数手がける。2010年に靴修理店「The Shoe of Life」を開業し、累計6万足以上を修理。2016年、作品「Return to the soil」が英国ノーザンプトン美術館に永久収蔵。2024年、国内靴ブランドとして初のB Corp認証を取得し、靴を起点にエシカルで持続可能なデザインを探求している。