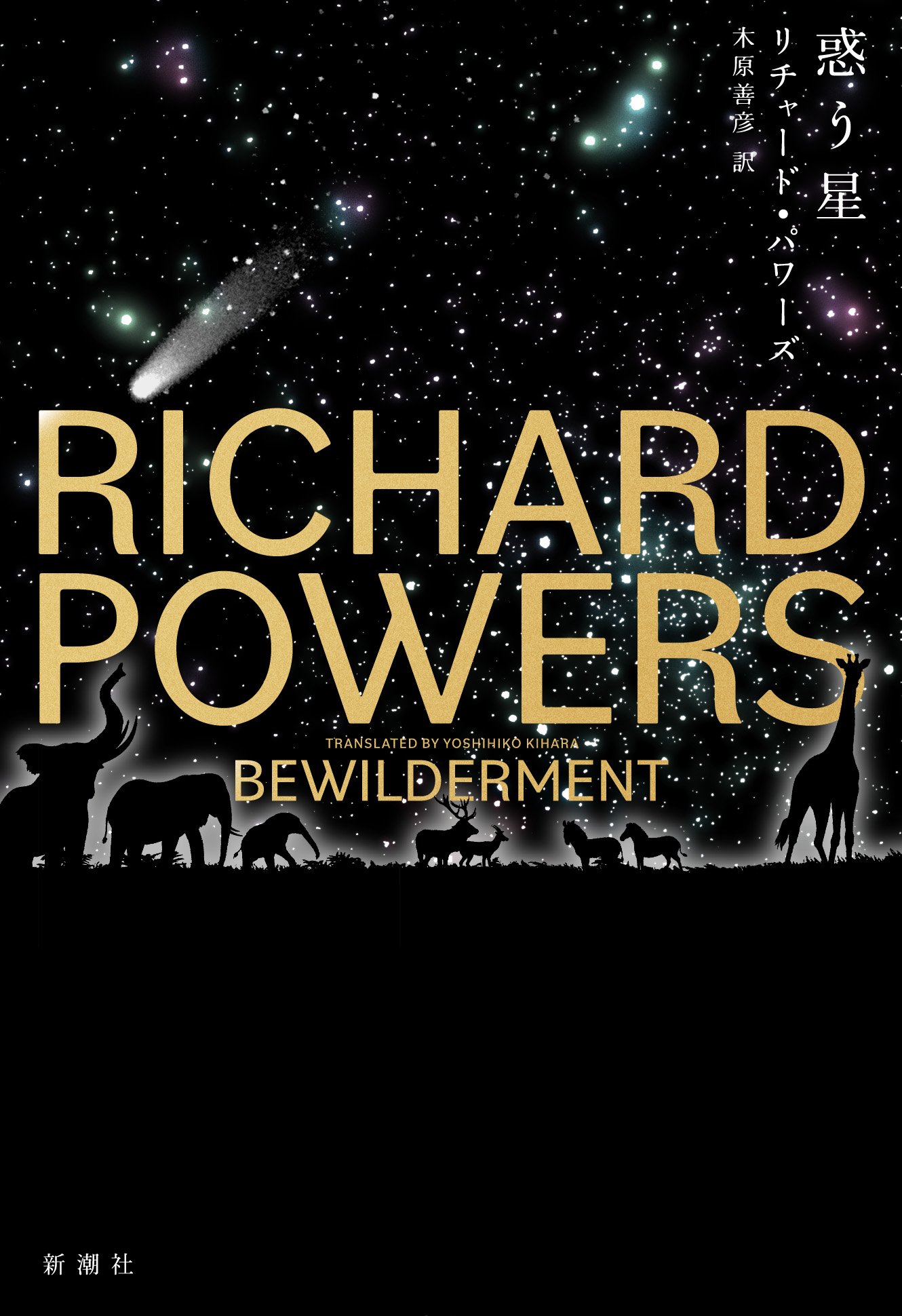【Penが選んだ、今月の読むべき1冊】
『惑う星』
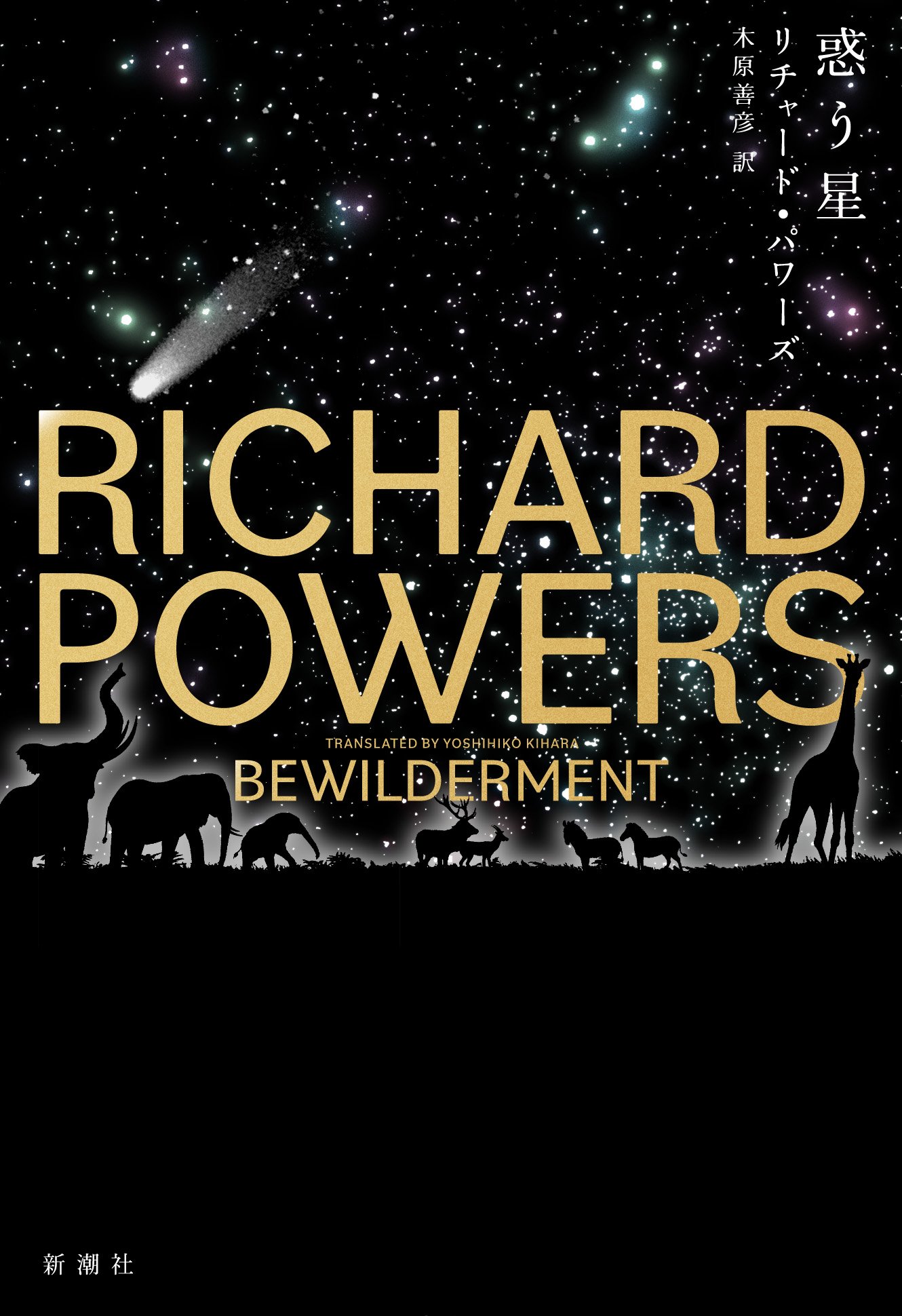
リチャード・パワーズの小説は、この世界を俯瞰して、もう一度見つめ直すための新しい地図のようだ。
前作『オーバー・ストーリー』でピュリッツアー賞を受賞。最新作『惑う星』は、地球外の生命を探す宇宙生物学者の父親と絶滅危惧種の動物に心を寄せる息子の物語だ。9歳になる息子のロビンは地球環境を憂いて、乳製品や卵を使った誕生日ケーキには一切手をつけないくらい、ほとんど絶望している。自然保護活動に打ち込んだ母親は彼が7歳の時に死んだ。情緒不安定になったロビンを、父親のシーオは山小屋に連れ出し、星を見上げながら話をする。この父と子の会話が、まずとてもいいのである。
少年は訊ねる。「地球が地球になるためには、どれだけたくさんのものが必要なの?」。
初めて清流の冷たい水に触れた彼に、父親が声をかける。「体の中にある両生類の本能を呼び覚ませ」。自然に身を委ねる時、時間軸は日常から解き放たれ、人は獣に還る。地球外生命は存在するのか。望遠鏡が幾多の信号を受信しても、明確な答えをいまだもてずにいる父親は、息子の疑問に答えるべく、寝物語に架空の惑星の話をする。地球の内と外、どこに希望を見出せばいいのか、試行錯誤するかのように。
ロビンのメンタルを治療するため、ある実験を試みたことから、物語はさらなる展開を見せる。人間の内なる宇宙と外側に広がる宇宙が相関的に響き合う世界観は、この作家の真骨頂であり、祈りに満ちた曼陀羅のようだ。『惑う星』とは、すなわち危機に瀕したこの地球であり、私たち人類こそがまぎれもない絶滅危惧種なのだと思い知らされる。子どもたちの絶望に、大人は一体どんな希望を用意してやることができるのだろう。現代アメリカ文学の知性が到達した、まぎれもない傑作。
---fadeinPager---
※この記事はPen 2023年2号より再編集した記事です。
---fadeinPager---
【画像】【Penが選んだ、今月の読むべき1冊】
『惑う星』