
一日の睡眠時間の世界平均は7〜8時間、日本人は特に短く、平均は 6〜7時間と言われている。忙しい日々の中で、いかに効率のよい睡眠をとるかに注目が集まり、パジャマやスマートウォッチなど、睡眠の質を上げるアイテムが多数登場している。
そんななか、睡眠のためのウエア「ズズズンスリープアパレルシステム」(ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM)」は、他とは一線を画すコンセプトとビジュアルで注目されている。このデザインを手掛けるのは、クリエイター集団のコネル(Konel)。なぜ、この「ズズズンスリープ」が生まれたのか? 他にもテクノロジーを使ったプロジェクトを多数手掛けるコネルが目指す場所について話を訊いた。
---fadeinPager---
まるで着る布団?! 「ズズズンスリープアパレルシステム」とは

ズズズンスリープアパレルシステムでは、大きめのダウンのほかに、ラグビー選手が着用するヘッドキャップのようなものも被る。ここから音が聞こえる仕組みだが、今後、脳波を測定する技術が導入されることも想定し、所々に穴が空いている。熱がこもりにくいという利点もある。
NTT DXパートナー(NTT東日本グループ)とコネルによって開発された「ズズズンスリープアパレルシステム」は、“眠りを持ち運ぶ”という新しい視点を提示する次世代型の睡眠ウェアだ。ベンチコートのような大きなコートと、ヘッドピース、指輪型デバイスを装着する。ヘッドピースにはヘッドフォンとLEDが搭載されており、指に付けた指輪型デバイス(SOXAI Ring)が、ユーザーの心拍数や体温、睡眠状態などの生体データをリアルタイムで測定し、その時の身体の状態に合わせてヘッドギアのオーディオや照明が変化し眠りに誘うという仕組みだ。
実際に体験してみると、温かく軽いダウンが心地よく、流れる音楽が心を落ち着かせ、自然に眠くなる。「ズズズンスリープアパレルシステム」は、10分や15分といった少しの時間に寝る「分眠」を推奨している。リモートワークが浸透し、ONとOFFが分けづらくなってきている現代で、こまめに睡眠を取ることで仕事や生活のパフォーマンスを上げようというものだ。コネルのクリエイティブ・ディレクターの宮田大はこう語る。
「日本にはもともと夜着(よぎ)と呼ばれる、着物状の形をした掛け布団がありました。袖と襟があり、身体全体を包み込むものです。少しの時間でもすぐに眠ることができるシステムを考えていた際にこの夜着を知り、『眠りを持ち運ぶ』というコンセプトにピッタリだと思いました。これは、ひと目でコンセプトを伝えられるようなインパクトのあるものになったと思っています」

心地のよい眠りを作り出す要素は音や光などさまざまだが、忘れてはならないのが温度だ。その時々の適温に調整しやすいよう、ダウンは光電子ダウンを採用。「遠赤外線セラミックス繊維」によって、体温エネルギーを積極的に活用できる。通常のダウンや化学繊維と比べて着用者自身の体温を衣類内部に“返す”ため、自然でやわらかな暖かさが持続しやすく、蒸れを感じにくい。
インパクトのあるシルエットで、ファッションとしても魅力的だ。しかし宮田はアパレルブランドになるのではなく、「ゴアテックス」のような技術のひとつになりたいと話す。
「さまざまなブランドの服や靴にゴアテックスが使われているように、最終的にはこの『ズズズンスリープアパレルシステム』が、さまざまなな服に導入されているようになりたいですね。雨を凌ぐためにゴアテックスの服を着て、日光が眩しければサングラスをかけるように、睡眠を大切にしたいからこれを着る、となると、カルチャーとしての睡眠がもっと大きな存在になっていくと思うんです」
---fadeinPager---
睡眠とテクノロジーの関係性
そもそもコネルが睡眠に着目したのは、これが最初ではない。2022年にはNTT東日本とソニー・ミュージックジャパンインターナショナルと協業し、洋楽を“ささやき声”でリアレンジする睡眠サウンドレーベル「ZZZN」を立ち上げ、3月の「世界睡眠の日」に合わせてシリーズ「ささやきララバイ(sasayaki lullaby)」をローンチした。バックスストリート・ボーイズやワン・ダイレクションなどの人気曲が、優しいウィスパーボイスで再構築された眠るための音楽だ。
これは子どもを寝かしつける際に自分も寝てしまったというコネルの仲間の体験から生まれたという。よくある睡眠用のリラックスミュージックではなく“ささやき声”というのがポイントだ。「子どものための子守唄を大人にも」という発想が面白い。
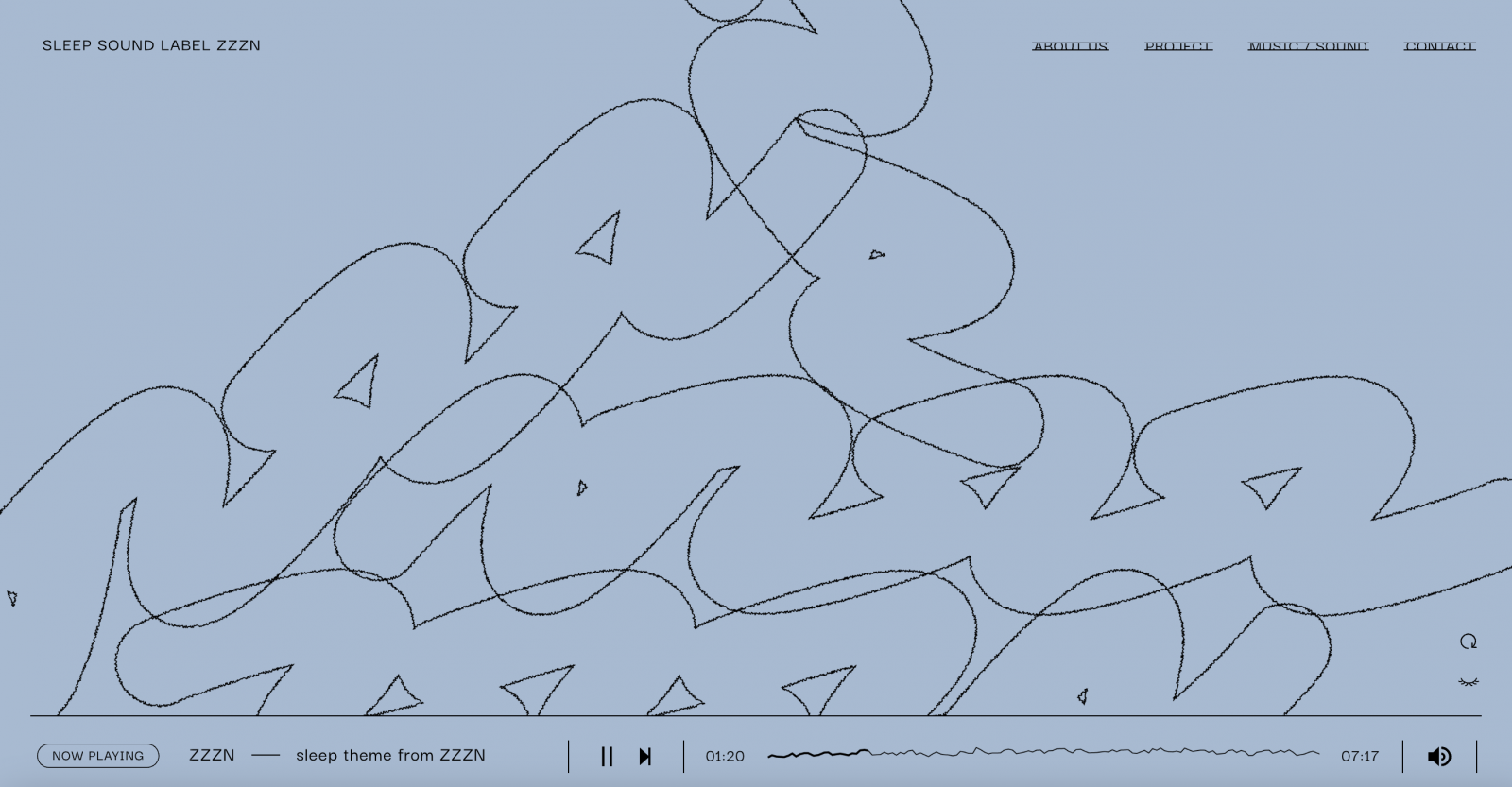
さらに23年には箱根のホテルで、「ZZZN(ズズズン)- LISTEN AND SLEEP -」という宿泊型睡眠ライブイベントも行った。NTT東日本、NTT DXパートナー、睡眠課題解決コミュニティ「ザコネ(ZAKONE)」、コネルによって実施。生演奏を聴きながら寝落ちするという宿泊型ライブイベントで、昼のライブでは大広間で雑魚寝しながら、アーティストたちの生演奏を鑑賞。夜は客室や庭園で、静かに聴きながら実際に眠ることができるという取り組みを行った。という取り組みを行った。
参加者は「ブレインスリープ コイン」という睡眠計測デバイスを身に着け、心拍や体動などのデータを計測。そのデータと連動して、客室や会場内の赤色LED照明が点灯・明滅し、参加者の“寝落ち”に合わせて徐々に暗くなる。寝落ちから10分後には完全に消灯する演出もされた。
心地良い睡眠のために科学的に計測を行い、音楽や環境をつくりだす。睡眠サウンドレーベル「ZZZN」や寝落ちイベントでの知見があったからこそ、この「ズズズンスリープ」へとつながっていったと言えるだろう。
箱根での宿泊型睡眠ライブイベントの様子
ブリジストンの技術が新しいかたちに。やわらかく包み込む「モーフ」

「ささやきララバイ」のように、自分たちの身近な体験や発見から、新しいものを発信してきたコネル。ブリヂストン ソフトロボティクス ベンチャーズと共同で生まれた「モーフ(Morph)」も、まさに自分たちならではの発見が生かされたプロジェクトだ。
モーフMorphは「何もせずにぼーっと過ごす」ための装置。ベッドのような大きな「モーフ」で、小型の「モーフ」を抱きかかえながら横たわると、柔らかな動きに包みこまれる。この動きは、象や人間の呼吸、空を飛ぶ鳥の翼、潮の満ち引きなど、自然界に存在する動きを、ラバーアクチュエーター(ゴム人工筋肉)によって再現している。この上に寝転ぶことで、不思議なリラックス状態を生み出す。
現代人は目的のない時間を持ちにくく、あえて「無目的な時間」を過ごすことが、新たな発想や豊かな時間へと繋がるのではないかという願いが込められている。このプロジェクトはブリヂストンのゴム人工筋肉の可能性を探る試みとして始まった。その技術は、ロボットの指先などに使われており、繊細な「つかむ」動作ができるという。コネルはこの人工筋肉を実際に遊びながら動かしてみることで、新たな可能性を探っていったという。

昨年、無目的室「モーフイン(Morph inn)」と題し、各地でイベントが行われた。
代表の出村光世はこう語る。「クライアントと対話を重ねることで、その会社やブランドの中に潜むものをシャープにしていくこともできますが、僕たちの場合は可能性を広げることのほうが得意だと思っています。「モーフ」も、まだどんな分野に応用できるかわかりませんが、実際に触って試すなかで発見した『面白さ』をそのままにかたちに落とし込み、大きな反響を得ました」
今後、この技術はオフィスの休憩室などに利用される可能性もあるだろう。睡眠、リラックスといった人間の身体と密接につながる部分と、テクノロジーを組み合わせるデザインアプローチで、「ありそうな未来」を描けることが、コネルの強みなのだ。
AIを使い、未来を引き寄せる

日本は年間の特許取得件数が30万件を超え、中国・アメリカに次ぐ世界第三位の特許大国だという。しかしそれが活用できておらず収益化できていないものがほとんどだ。無料版もあり、Proプランは月額41,500円から利用ができる。
出村は、コネルでの取り組みは「あり得る未来、いい未来を引き寄せる」ことだという。
「以前から、人工知能が人類の知能を超えるシンギュラリティが2045年頃に訪れると予測されており、その到来は技術革新によってさらに早まっていると言われています。人間にとって人工知能が敵になる未来を考えるよりも、ポジティブな未来を提示することが、良い未来につながっていくと思っています」
これからの未来を考える上で避けては通れないAIの分野。昨年、公開されている特許情報をAIで要約し、それをもとに大量の事業アイデアを生み出すことができるアイデア共創プラットフォーム「アイデアフロー(ideaflow)」を立ち上げた。専門的で分かりにくい特許をAIが要約し、アイデアの提案やAIとの対話によるブラッシュアップできるというサービスだ。

人工知能が介在する創造の現場で、人類が安心して表現できる“余白”を整えることを目指す「ai-ai」
さらに今年7月には“生成AI”に特化した専門チーム「ai-ai」を発表。AIを使うハードルは下がったものの、クオリティの高い画像をつくったり、著作権やセキュリティの問題などビジネスに活用するにはまだまだハードルが高い。そこで、AIを使った新規事業やクリエイティブを支えるチームを発足させた。
「AIは人類の拡張であり、真に大きな進化は“人間側の再発明”にある」というビジョンのもと、「AIを単なる道具にとどめず、共生する仲間として使いこなす」ための実践的なプロジェクトを推進している。テクノロジーを身近なものに引き寄せ、使いこなすことが、一歩ずつだが着実に良い未来へとつながっていく。





