Pen本誌では毎号、作家・小川哲がエッセイ『はみだす大人の処世術』を寄稿。ここでは同連載で過去に掲載したものを公開したい。
“人の世は住みにくい”のはいつの時代も変わらない。日常の煩わしい場面で小川が実践している、一風変わった処世術を披露する。第6回のキーワードは「マイNGワード」。
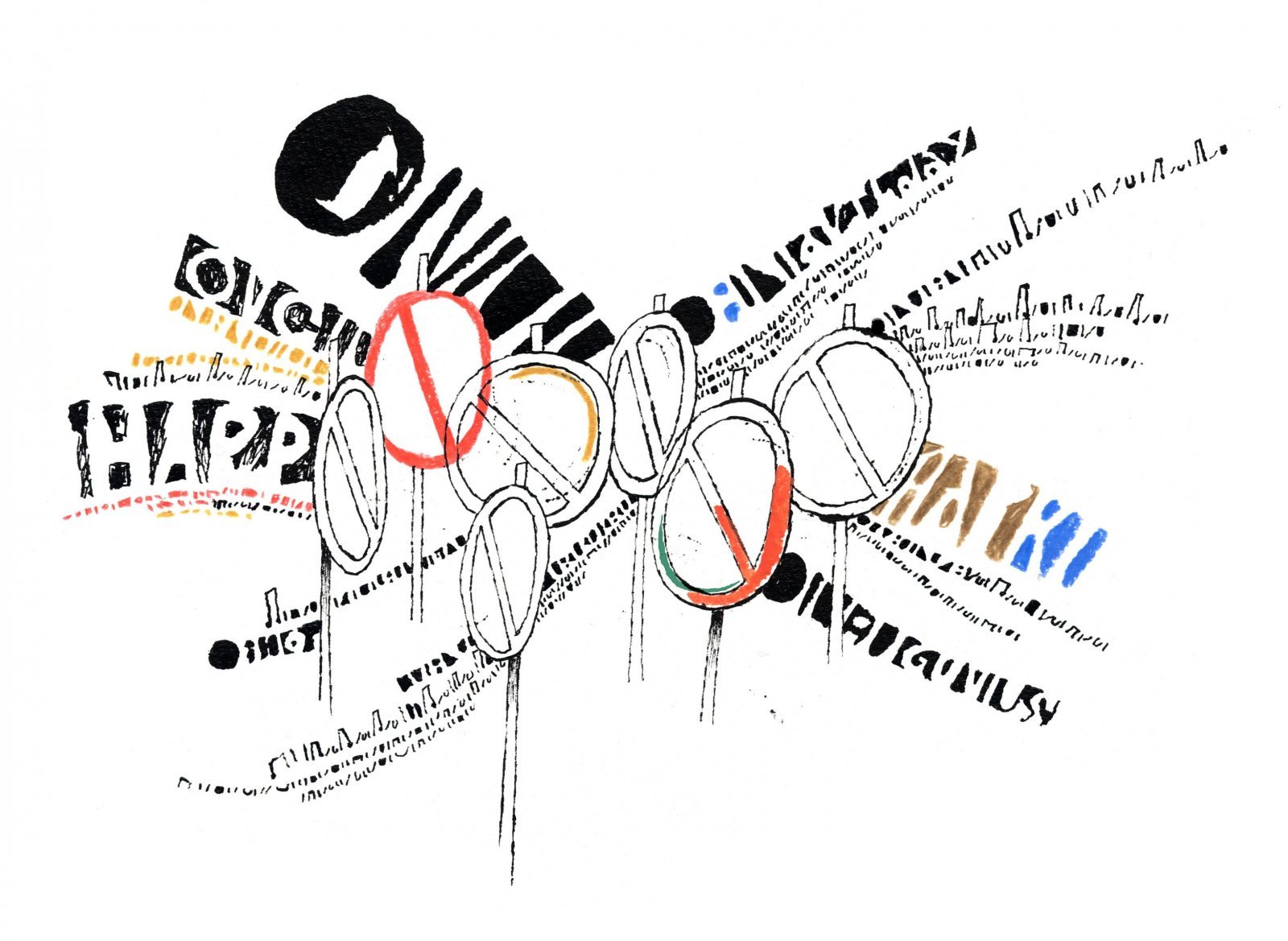
他人が使うのは一向に構わないのだが、自分では絶対に使わない日本語が存在する。僕の場合は、「フィックス」とか「リスケ」とか「ジャストアイデア」みたいなビジネス用語だったり、「チルい」とか「Z世代」みたいな新語だったりする。そういった言葉は、意味はだいたいわかるのだが、なんというか僕の内臓に染みていないので、口にしようという発想にならない。
「なにを口にするか」「なにを口にしないのか」という基準は人それぞれ異なるものだ。とりわけ、こういった比較的歴史の浅い言葉は、年齢や世代によって使う基準が大きく変わってくるだろう。先輩作家は「コスパ」とか「ヤバい」とか「マジで」という言葉は絶対に自分では使わないといっていた。確かに、30代半ばの僕にとっては若い頃から馴染みある言葉だが、上の世代にとってはそうではないかもしれない。
問題は、歴史の浅い言葉ではなく、古くから存在する日本語の中にも、自分で使うことのできない言葉があることだ。
たとえば僕は誰かに向かって「愛してる」とか「好きだ」という言葉を発することができない(その事実がどういう問題を生むかは、なんとなく察していただけるとありがたい)。もちろん、何者かに監禁されて、「いますぐ『愛してる』と口にしないと右腕を切断する」などと脅された場合には口にする。でも、自分の意志で発声することはできない。そういう言葉を口にするだけなら誰でもできる。だから、喋った途端に軽くなってしまうというか、嘘になってしまうような気がするのだ。
それ以外にも、僕が誰かに向かって口にできない言葉はたくさんある。「尊敬している」や「天才」もそうだ。このふたつについては、本質的に誰かを尊敬したり、天才だと思ったりすることがないからだと思う。誰かが成し遂げた偉業や、誰かが残した作品に感動したり、率直にすごいと思ったりすることは人並みにあるのだが、その人物を尊敬したり、天才だと思ったりする感覚があまりない。どんな偉業やどんな作品も、僕と同じ人間が、ある過程を経て生み出すもので、その過程をたたえるだけで十分だと思ってしまう(僕よりもずっとひどいのが父だ。「ごめんなさい」や「ありがとう」が口にできない。だから友達がひとりもいない。父と違い、僕は口にできる)。
ここから先は理解不能な領域になっていくと思うが、「誕生日おめでとう」という言葉も口にできない。根本的に、誕生日というものをめでたいと思っていないからだ。誕生日は、生まれてきた以上、誰でももっているものだ。誕生日をもつことにも、誕生日を維持することにも、なんの努力も才能も要らない。高齢の老人ならまだしも、ただ漫然と誕生日を迎えることなんて誰でも達成できる。そんなイベントを祝おうという気持ちがどうしても生まれない。
「誕生日おめでとう」よりもっと嫌なのが「あけましておめでとう」だ。人間がきわめて恣意的につくった暦というシステムが、ただ単に更新される、というだけのイベントのなにがめでたいのかわからない。それ故、新年に知人に会い、「あけましておめでとうございます」と言われると、僕はいつも気まずい思いをしながら、小さい声で「どうも」や「はい」と口にしている。
そこまで書いて、「おめでとう」という日本語を辞書で調べてみたところ、「新年や慶事にあたってのあいさつの言葉」と出てきた。どうやら世間の使い方のほうが正しかったようだ。僕の「おめでとう」の使い方が間違っていた。変なことを主張してしまい「ごめんなさい」。
小川 哲
1986年、千葉県生まれ。2015年に『ユートロニカのこちら側』(早川書房)でデビューした。『ゲームの王国』(早川書房)が18年に第38回日本SF大賞と第31回山本周五郎賞受賞。23年1月に『地図と拳』(集英社)で第168回直木賞受賞。近著に『君のクイズ』(朝日新聞出版)がある。
※この記事はPen 2023年6月号より再編集した記事です。