Pen本誌では毎号、作家・小川哲がエッセイ『はみだす大人の処世術』を寄稿。ここでは同連載で過去に掲載したものを公開したい。
“人の世は住みにくい”のはいつの時代も変わらない。日常の煩わしい場面で小川が実践している、一風変わった処世術を披露する。第3回のキーワードは「捏造人生」。
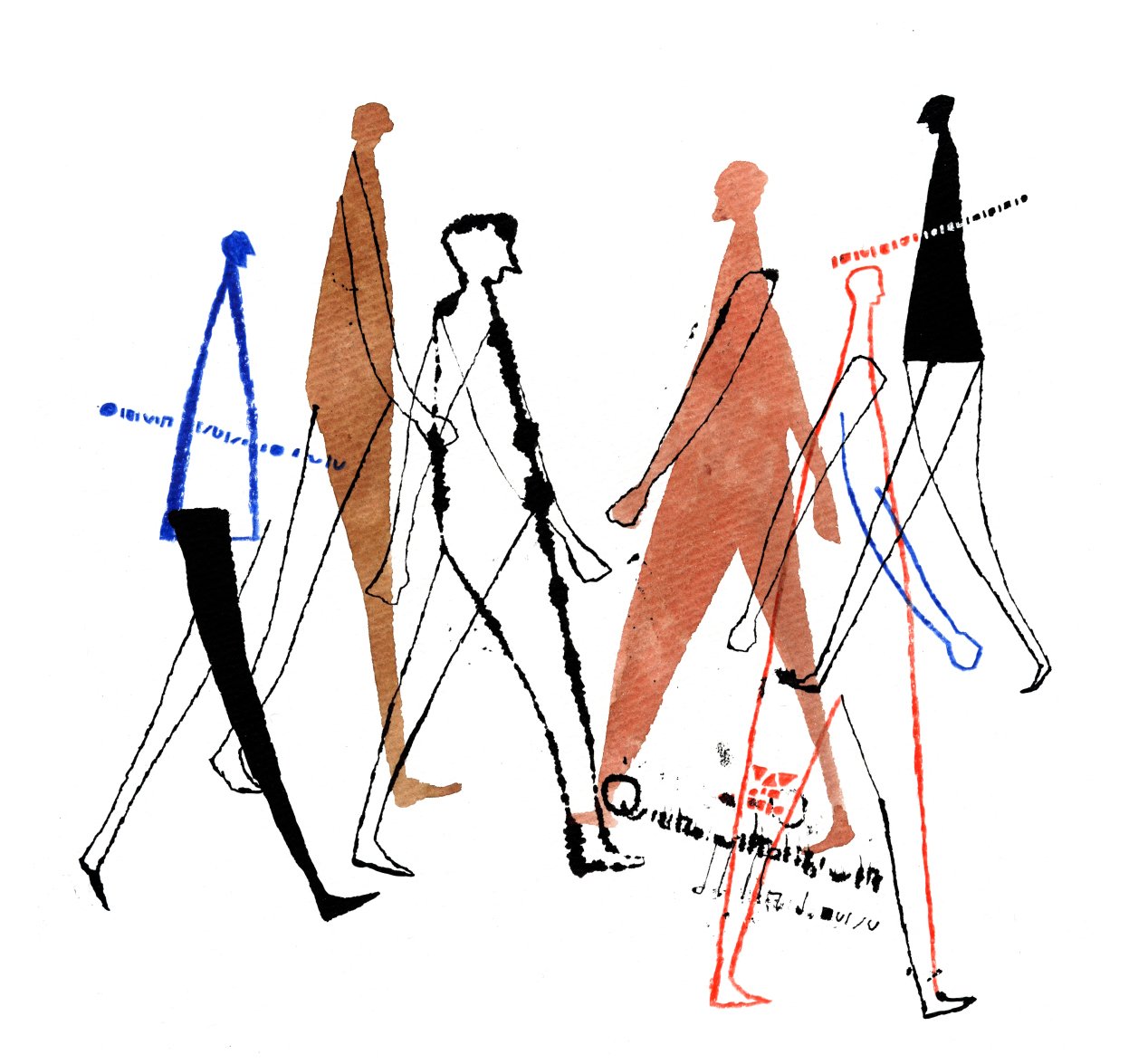
小説を書いて本が出ると、取材依頼を受けることがある。それなりの数の依頼があった時、わざわざ何回も出かけるのが面倒なので、僕は同日にまとめてスケジュールを組んでもらう。そうなると、朝から晩までさまざまな記者に向かって自作の話について語り続けることになる。
世の中には、広く読まれる価値があるのに、日の目を見ないまま埋もれてしまう出版物も多い。そのことを考えれば、そもそも取材依頼があること自体、とてもありがたい話だ。だから僕は可能な限り取材を受けるようにしているのだが、そのせいで奇妙な問題に悩まされることになる。
取材では、ほとんどの場合、同じようなことを聞かれる。「この本を執筆しようと思ったきっかけはなんですか?」というやつだ。もちろん記者に悪気がないことは知っているし、僕のことを知らない人に向けて記事を書く時に、必要な質問だということもわかっている。でも、「そんなこと、わかんねえよ」というのが、正直な気持ちだ。
まず、期間の問題がある。本が出て、その本を読んだ記者が取材を申し込んでいるということは、既に執筆を終えてから少なくとも半年以上は経っている。執筆を終えて半年以上経っているということは、執筆を始めた瞬間からは1年かそれ以上経っているということを意味する。そんな昔のことは正確に覚えていないのが普通だろう。想像してみてほしい。たとえば街で知らない人に話しかけられて「最初に自転車に乗ろうと思ったきっかけはなんですか?」と聞かれたら、困惑する人も多いはずだ。「みんなが乗っていたから」とか「格好いいと思ったから」とか、その程度のことしか答えられないのではないか。
期間の問題をクリアしたとしても、質問の内容が難しいという問題がある。そもそも「きっかけ」とはなんだろうか。ラーメンを食べるきっかけの多くは「腹が減っていたから」だが、執筆のきっかけを「書きたかったから」と答えていては記事にならない。なぜカレーやハンバーガーではなくラーメンなのか、自分でよくわかっていなくても、答えを捻り出さなければならない。
そしてなにより、同じ質問に答え続けることに飽きてくるし、取材に同席する担当編集者に「何度も同じ話を聞かせて申し訳ない」という気分にもなってくる。以前、繰り返しに飽きた僕が、聞かれるたびに「執筆のきっかけ」をその場ででっち上げて話していたら、記事ごとに整合性が取れなくなって大変なことになった経験もある。
そんなこともあって最近では毎回同じ話をしているのだが、それはそれで大きな問題がある。何度も話すうちに「執筆のきっかけ」の話が洗練され、シンプルでわかりやすく、記事にしやすい「誕生秘話」がなんとなく出来上がってしまうのだ。
僕自身は経験がないのだが、たとえば就活でも似たような現象が発生するだろう。歓楽街で豪遊するために東南アジアへ旅行していた人物が、就活を繰り返すうちに「見聞を広めるため」に海外へ渡航していたことになっていたり、異性と出会うためにテニスサークルに入った人物が「スポーツの素晴らしさ」を語り始めたりする。
新しくなにかを始める理由なんていつも複雑だし、いろんな偶然が重なるものだ。短い時間で「〇〇だからです」と答えられる時ほど、自分の人生を捏造しているのではないかと心配したほうがいい。しかし、そんな前提を深く理解した上で、やはり「〇〇だからです」と端的に答え、自分自身に嘘をつくこと ̶ ̶それこそが「大人である」ということかもしれない。
小川 哲
1986年、千葉県生まれ。2015年に『ユートロニカのこちら側』(早川書房)でデビュー。17年『ゲームの王国』(早川書房)が第38回日本SF大賞と第31回山本周五郎賞受賞。近著に『地図と拳』(集英社)や『君のクイズ』(朝日新聞出版)がある。
※この記事はPen 2023年3月号より再編集した記事です。