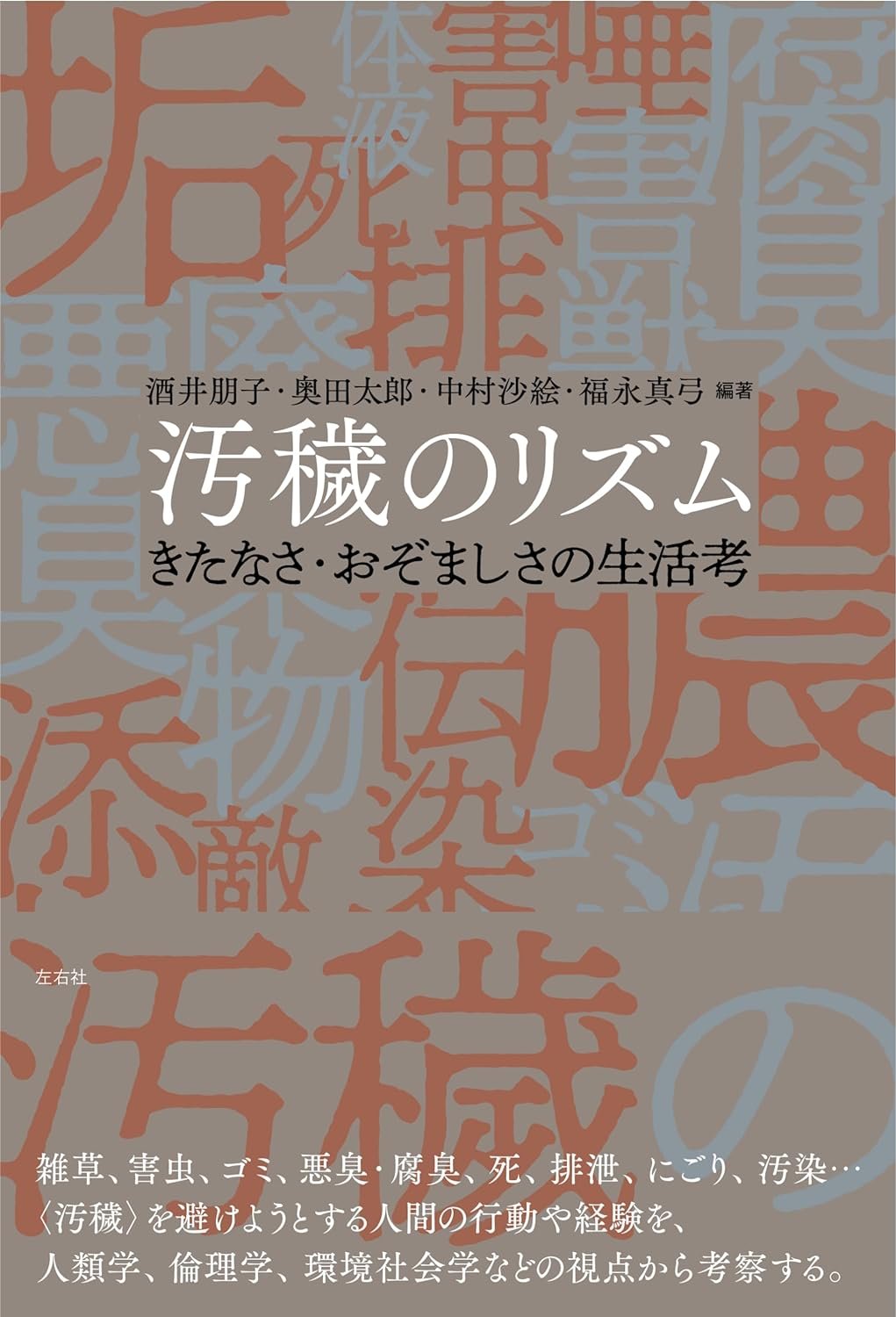【Penが選んだ、今月の読むべき1冊】
『汚穢のリズム きたなさ・おぞましさの生活考』
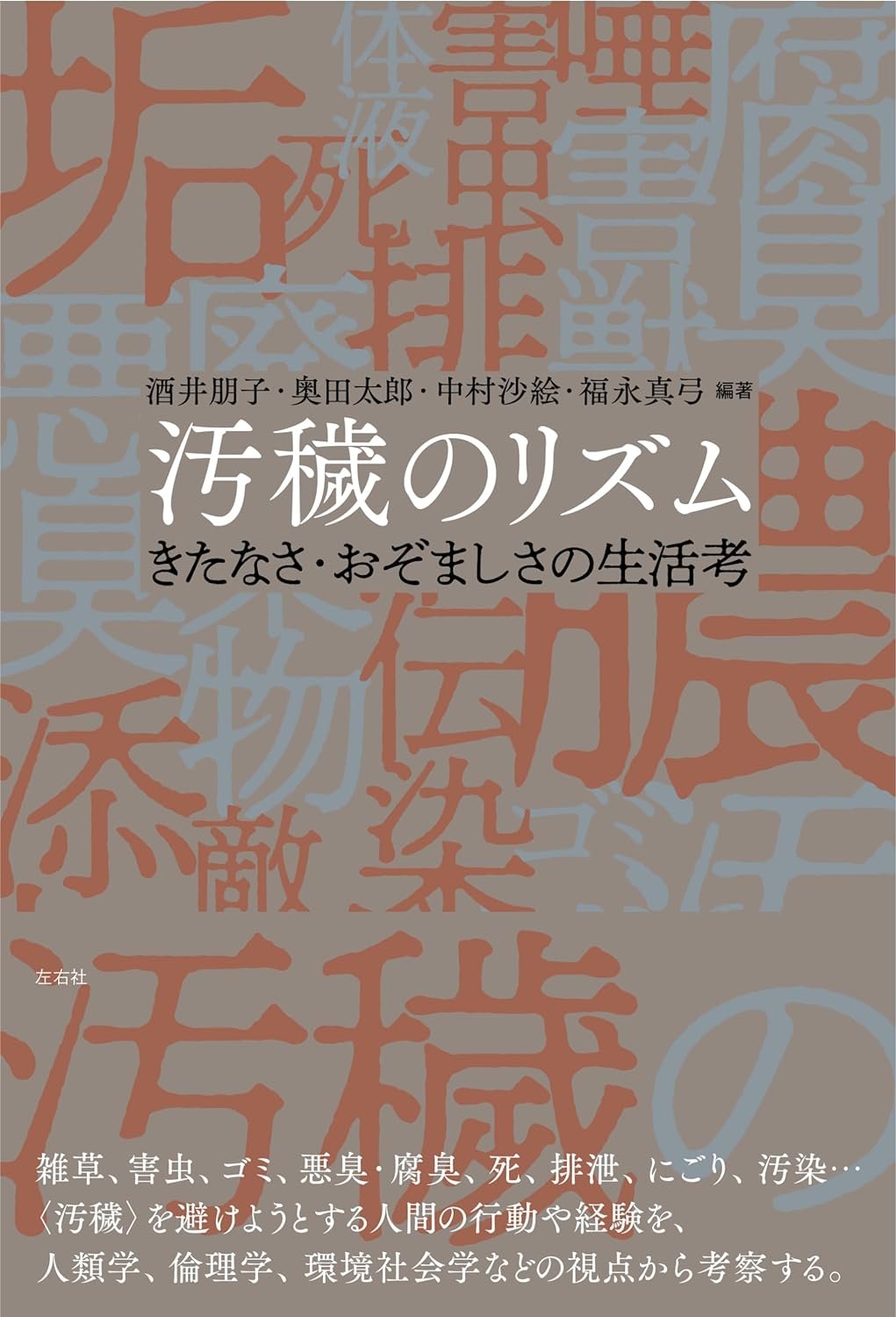
日常生活を送るなかで、「汚穢(おわい)」という単語に触れる機会は決して多くない。「きたないもの」を指すだけに、無意識のうちに敬遠したくなるのだろう。だが、実際のところそれは、我々と密接な関係にある。編者が本書の目的を、「汚穢のなかから、汚穢として脈打ちつつ、ものを考えようとしている」と表現しているのも、さまざまな汚穢が私たちに近しい存在であるという“本質”を浮き上がらせるためだ。
本書ではそうした考え方に基づき、複数の書き手が汚穢にまつわる各人の体験を軸としつつ、さまざまな人間の在り方を考察する。そのため「きたないもの、おぞましいもの」として扱われる汚穢も、雑草、害虫、ゴミ、悪臭、腐臭、死、排泄、にごり、汚染など多様だ。
汚穢が対象である以上、読み進めていけば不快な気分になることも十分に考えられる。ところが少なくとも個人的には、表層としての不快感を超越した“本質的ななにか”を感じた。いい例が、「日本のどこかの、とある介護施設」で生きる老女の排泄の情景が“ありふれた一場面”として淡々と綴られる章「巻き込まれる――介助と排泄といくつもの生」だ。排泄は汚穢と直結しているだけに、読むには多少の決断が必要となるかもしれないと最初は感じた。だが読み終えてみると、不思議なことに不快感は残らなかった。それどころか、介助を受ける老女が静かに隠そうとしている恥じらいのような繊細な感情までもが、文脈から伝わってきたのだ。そのため読後には、心の奥をある種の心地よい感情がすっと通り抜けていくような気さえした。それは、汚穢を媒介して本質が浮かび上がったからなのだろう。
言い換えれば汚穢とは、「きたない」という短絡的な表現を超えた概念なのである。
※この記事はPen 2024年6月号より再編集した記事です。