【評者】池上英洋(美術史家・東京造形大学教授)
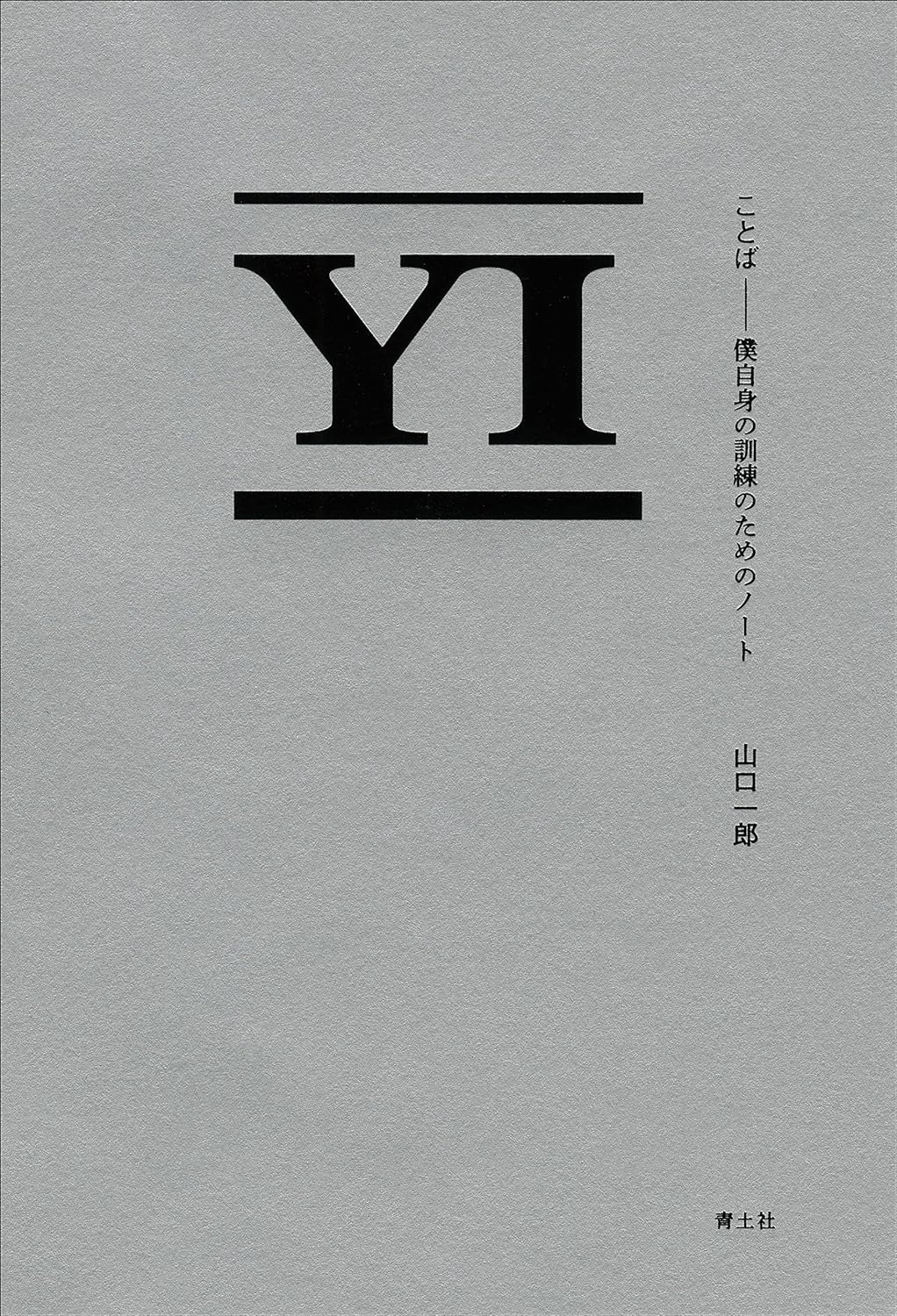
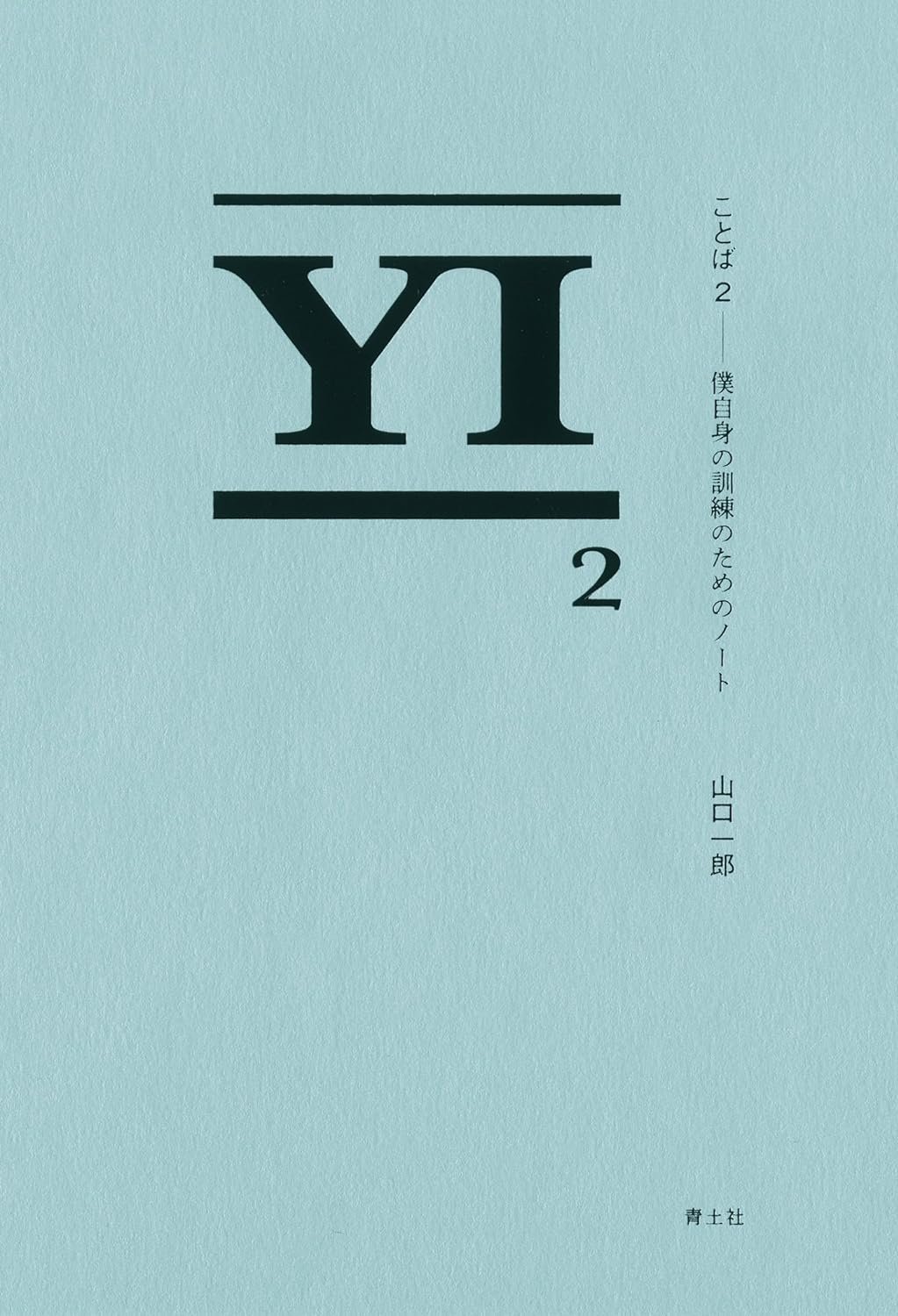
私の歌を聴くために、船の後ろを小舟で付いてくる者たちよ、元の浜辺に戻りたまえ
また大海原へ漕ぎ出せば、いつか私の姿を見失い、ただ漂うだけになるのだから。
―ダンテ・アリギエーリ『神曲〈天国篇〉』第二歌より(評者訳)
山口一郎本人が語っているように、彼の作品世界には、音楽よりもまず先に言葉があり、詩がある。稀代のメロディメーカーたる山口に対して意外に思われるかもしれないが、彼はむしろ自身の詩を伝えるための手段としてこそ、歌を選んだとさえ言える。だから、サカナクションの楽曲について「文学的、抒情的」といった形容がよく用いられるのはごく当然であって、想像するにおそらく彼はメロディよりも言葉を紡ぎ出すプロセスにより多くのエネルギーを費やすのだろう。実際に、部屋にこもって何日ももがいた末に、ようやく朝方になって疲弊しきった顔で歌詞ができたことを告げる山口の姿は、SNSなどで彼をフォローするファンたちの間ではよく知られている。
そうやって生みだされた山口の言葉は、リズムやメロディにのせなければならないという制約はあるが、現代詩そのものと言える存在である。いや、俳句や短歌に語数や季語といった制約があるからこその長所があるように、山口の詩にも音楽からの縛りが時に助けとなっているに違いない。彼自身、リズムが言葉を凌駕する瞬間があると語っている。ともあれ彼が音楽を詩の伝達手段として選んだのが正しかったことは、サカナクションの楽曲を愛する人の多くが、その歌詞を心を揺さぶられる理由のひとつとしていることで証明されている。実のところ、今日の日本で、彼ほどに多くの作品を読まれている詩人もそう多くはないだろう。
父・山口保の編纂で各250篇の詩を収録
『ことば(YI)』と『ことば 2(YI 2)』は、山口が二十歳前後からメジャーデビューする頃まで書き綴った詩を集めた本である。いずれも250篇ずつの詩が編まれた山口初の著書であるが、発案も編纂も父である山口保による。学生運動あがりで看板画工や議員を経て木彫工房を営んでいるこの変わり種の父から一郎は多大な影響を受けており、幼い頃から文学に親しむようになったのも父の働きかけによる。サブタイトルが示すように「訓練のため」に、ガラケーで毎日ポチポチと、出版を意図することなく打っていた詩を本にすることに一郎本人は抵抗があったようだが、父になかば押し切られた形で同書は世に出た。ただ、装丁だけは一郎のたっての希望で葛西薫が担当している(ちなみに葛西は評者が勤務する美大の客員教授で、また金属光沢を放つ限定版の布クロスも名誉教授の須藤玲子によるものなので、評者は同書に勝手に縁を感じてしまう)。鋳造活字で組まれた活版印刷も、かすかなカスレやにじみによって文字に個性を与えている。
僕らは小さくススキのように頼りないが、決して一本ではない。落ち着かない春風は主流派という波を作り、少数派の僕らまで根ごと毟りとろうとするんだ。―『ことば』「やったらやり返される」より
楽曲作りの時期と重なっていることもあって、当然ながらサカナクションの曲に繋がる詩も多い。たとえば「G0 TO THE FUTURE」そっくりの詩もあれば、上に引用した詩などは後の「モス」を彷彿とさせる。夜や波、月や煙といった彼の歌詞によく登場する言葉は、詩集でもすでにしばしばあらわれている。内容は個人的な体験やエリアを対象としたものが多いが、「日本は変わらなければならない」(『ことば』「ナンドデモ」より)といった直截的な社会的発言も時に混じる。両面性があるのは当然のことで、淋しさや孤独、ゆらゆらと漂うやや不安定な感覚が支配するなかで、テレビ番組などで見せるハイテンションな山口も時おり顔をのぞかせる。そのどちらもが山口がもつ顔であり、ガラケーで発表していた点である程度の公共性を有してはいたが、出版を意図していなかったからこそ、そこには当時の彼の感情がむき出しに近い形で吐露されているはずだ。実際に、ビクターの傘下レーベルにいた頃に彼が一路の筆名で書いていたブログの中で、彼自身が次のように述べていた。
僕がまだフリーターだった頃の、熱く文学的思想にもやもやしていた時代の言葉を今読んでみたら、毬栗の棘みたいにギラギラでした―ブログ「テクノクション語録」2008年9月「昔に書いた詩を読んでみた」より
二冊の『ことば』は、打ち寄せる言葉の波間から、まさにこの「ギラギラした棘」を掬って拾い集めたものにほかならない。
受け手があらたなイメージを創り出す源泉に
ただ山口は以前、評者との対談の中で、「昔書いたものをもし後世の人に勝手に読まれたりしたらショックだ」と話していた(「ダ・ヴィンチ没後500年記念“夢の実現展”トーク」2020年1月)。まさに「昔書いたものを人に読まれる」形となった『ことば』は、若かりし日の山口にとっては憤慨すべき暴挙なのかもしれない。しかし現在の山口は過去の自分をやや鳥瞰図のように客観視しているようで、かつての自分が断固として抱えこんでいた「あるべき姿」に固執していない。先に引用したブログ記事には、実は「僕はあの頃の僕へ心を遷都するために、今尽力しております」との文が続く。そこから今に至る変化の過程には、コロナ禍と、それを契機として彼の中で顕在化してしまった鬱の存在がある。そのことを公表した番組の中で、彼は鬱との格闘の果てに、以前と同じ状態にはならないだろうことを受け容れざるをえなかったことで、「戻るんじゃなく、新しくなればいい」という心境に至ったと述べている(NHKスペシャル「山口一郎“うつ”と生きる~サカナクション 復活への日々~」2024年より)。同様の言葉は復活ライブツアー「SAKANAQUARIUM 2024“turn”」でも、変わっていく“あらたなサカナクション”としてファンに向かって投げられている。
結局のところ、山口自身にとって『ことば』は過去の自分の熱情を少し思い出させてくれるものでしかなく、評価を気にする対象でもないはずで、つまり本人にとっては書評記事などもさして意味をもたない。しかし私たち読者にとっては、ある詩人の純粋なる詩集として、また彼の作品世界が構築されていった過程を追走できる興味深い足跡であり、さらにはそこから一人ひとりが新たなイメージを創り出す源泉にさえなりうる。というのも、あらゆる芸術は作者の手を離れた瞬間から受容者(受け手)のものとなる宿命だからだ。創り手がいかなる想いやメッセージを込めようと、それをいかに解釈するかは受け手一人ひとりの脳内での再構成如何にかかっている。
その点で、私たちが忘れてはならないことがある。それは、『ことば』や彼の歌詞に書かれていることがすべて、山口の真の姿を完全に映し出していると誤解しないことだ。これは当然のことではあるのだが、山口の言葉がとりわけ内省的でかつ物語性が強いため、ともするとそれらはすべて山口の個人的実体験の産物であるかのようにとらえられやすい。そのため人によっては強く共感し、なかにはまるで自らの鏡像かのように同化する者もいれば、あるいは反発する人だっているだろう。
---fadeinPager---
創作に不可欠な要素であろう、圧倒的孤独感
しかし、私小説の多くが同時にフィクションでもあるように、彼の詩もまた、彼自身の言によれば「フィクションであり、ノンフィクションでもある」(前掲した評者との対談より)。彼は歌作りの変化について、「以前は自分の心に浮かんだものだけを歌っていた。でもちっぽけな自分の想像力なんてたかがしれてるんじゃないか、そう思い始めた」(NHK「東京ナイトフィッシング」2016年より)とも述べている。だからこそ、「自分が描いていたイメージを超えるもの、裏切るもの」(同前)である「違和感」を求めて、山口は夜の街を彷徨う。そしてシーラカンスのように、暗い海の中を漂う。そうしている間、彼のまわりにあるのは(たとえそれが街中の喧噪であろうと)圧倒的な孤独感であるに違いない。
そのことが彼を際限なく苦しめる一方で、同時にそれは創作に不可欠な要素でもあるのだろう。山口は同番組の中で、家庭持ちのディレクターに対し、「病気もできない、無理もできない、俺、そんな状態で歌詞書けるのか心配」(同前)と率直に吐露している。その姿は、ミューズ(詩神)を前にして「詩人たちの苦悶の日々は永遠に続く」と詠んだボードレールの詩を思い出させる(シャルル・ボードレール「美」より、評者訳)。
傷だらけの指で土を掻くように、痛みなくしては何も生まれないように焦ることなく僕は生きよう。―『ことば2』「太陽」より
歌を作るためには、苦しまなければならない。―ほぼ確実に、そう山口は自らに言い聞かせてきたのだろう。苦悩する多くの人々が共感を覚えるのも自然なことだ。ただ山口本人も言っているように、彼は共感されようと思って書いているわけではない。いつの間にかスターとなり、ステージ上で手を振れば群衆が一斉に同じ動きをすることに抱いた違和感は「アイデンティティ」に歌われている通りだ。まるで教祖かなにかのように偶像視され、一種のアイコンともなった自分自身に、これで良いのかと自問し続けてきた山口は、膨らみ続ける重責を放り出したく思ったこともそれこそ無数にあるだろう。冒頭に訳出した詩はダンテの『神曲』の一節だが、おそらくは少し前の山口の心情に重なるものと想像する。まるで、そこまでの責任を負わせないでくれ、と叫んでいるような詩だから。
「去年と同じ服を着て、去年と違う自分に気づく」(同「ループ」より)。25歳の時の詩の一節だが、普遍性をもつこの言葉は今の山口とサカナクションにこそ相応しい。もはや昔の自分たちには戻れないし、戻る必要もない。これまでの山口とサカナクションがそのままの姿であり続ける部分に、あらたに変わっていく部分が加わっていく。彼が言うように、曲と離れた形式での“純粋に文学的な”詩作は今の山口には難しいかもしれない。現代詩も愛する身としては若干の淋しさはあるが、これから先、山口がどう変わっていくのかは予測がつかないし、おそらく本人にも分からないだろう。当分の間は増え続けるだろう歌詞を彼の文学作品のひとつとして楽しみながら、二冊の『ことば』の読者としては500篇の詩を自分で味わい続けるしかない。先に書いたように、受容者である私たちには、作品を再構成して独自のイメージを創りあげる自由があるのだから―。
よもや時代の最先端。(中略)どうかその先に何があるかいつか僕にも解るようになりますように。―同「拝啓哲学」より