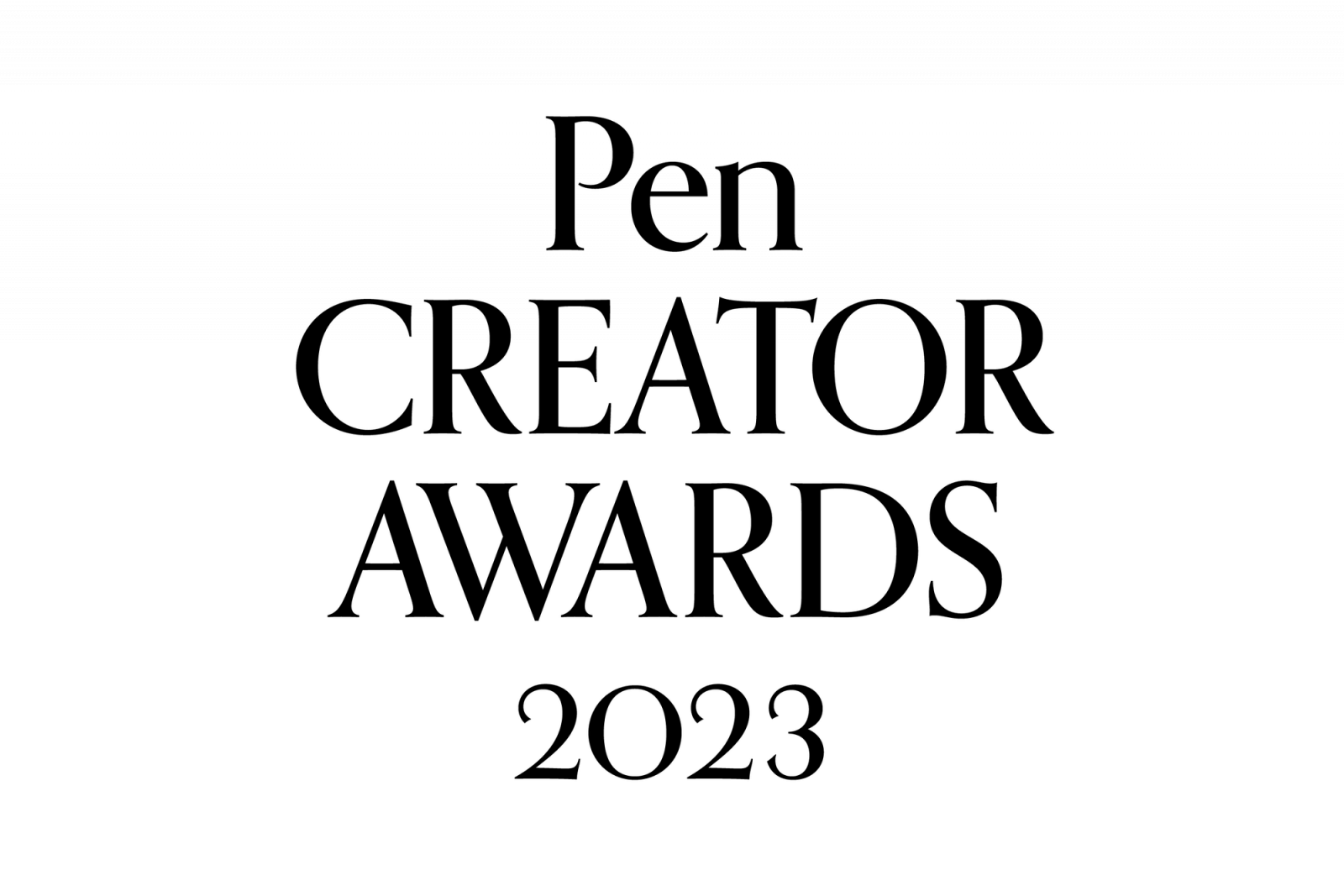サックス奏者・作曲家、松丸契のことをまだ知らない人は、ひとまずなにも読まずに彼が2022年にリリースした2ndアルバム『The Moon, Its Recollections Abstracted』を聴いてほしい。記録されている音、それ以上でも以下でもない、完璧な一つの世界が立ち上がるセンセーションをまっさらな状態で体験することは、他に代えのきかないものだ。
幼少期から高校卒業までをパプアニューギニアの山村で過ごし、アメリカ・バークリー音楽大学を卒業したのち、2018年から東京で活動を開始した松丸。R&Bやヒップ・ホップしか聴いてこなかった少年時代を経て、プロパーな音楽教育およびジャズのコンテクストを学びながらも、それにあえて“背を向ける”ことを選んだ彼がいま、シーンやジャンルを問わず多様なアーティストと共演し、マージナルで独創的な音楽家として注目を受ける、その理由とは。
普段、松丸がレコーディングに使用しているという池袋のスタジオ「STUDIO Dede」にて、映画『白鍵と黒鍵の間に』で俳優にも初挑戦した松丸の2023年を振り返ってもらいつつ、彼が考える新しい音楽の在処やクリエイティブの起点、芸術家としてのスタンスについて、じっくりと話を訊いた。

BREAKING by Pen CREATOR AWARDS 2023
確かな才能で存在感を強める、いま注目すべきクリエイターをいち早く紹介。アート、食、ファッションなど、各界のシーンで異彩を放つ彼らのクリエイションと、そのバックボーンに迫る。
---fadeinPager---
Pick Up Works

『The Moon, Its Recollections Abstracted』
2022年10月に発表された2ndアルバム。『即興と作曲の対比と融合』と『具体化と抽象化』をコンセプトに制作。金澤英明(Bass)、石井彰(Piano, Rhodes)、石若駿(Drums, Percussion)、石橋英子(Vocal, Flute, Electronics)が参加した。ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文が主催する、新進気鋭のミュージシャンが制作したアルバムに送られる「Apple Vinegar Award 2023」を受賞。

『白鍵と黒鍵の間に』
2023年10月6日より公開された池松壮亮主演、冨永昌敬監督の映画。松丸が参加するバンド、SMTKの楽曲「Headhunters (feat. Dos Monos)」のPVを冨永が監督した縁から出演が決定。エッセイスト・ジャズミュージシャンの南博による回想録『白鍵と黒鍵の間に−ジャズピアニスト・エレジー銀座編−』を原作とし、昭和末期の夜の銀座を舞台に、ジャズピアニスト志望の青年と夢を諦めた男の運命が交錯するドラマを描く。松丸は主人公の友人であるサックス奏者、「K助」を演じた。
---fadeinPager---
名前がついていないものの方が、可能性を秘めている

1995年生まれ、パプアニューギニア出身。標高1500メートルの村で育ち、高校卒業まで独学で楽器を習得、2014年に渡米。音大卒業後の18年からは日本を拠点にさまざまなアーティストと共演する。21年には東京都現代美術館「Christian Marclay Translating」展でジム・オルーク率いるバンドの演奏に参加。SMTKやm°feでも活動し、アルバムをリリースする。20年に1stアルバム『Nothing Unspoken Under the Sun』を、22年に2ndアルバム『The Moon, Its Recollections Abstracted』 を発表。2020年より90分のアコースティックな即興演奏を通して空間と時間と楽器と身体の関係性を探る「独奏」を活動の一環として開始。多岐にわたる音楽的活動を展開している。
――2023年の松丸さんの活動は、22年リリースした2ndアルバム『The Moon, Its Recollections Abstracted』のツアーでスタートしました。金澤英明さん(Bass)、石井彰さん(Piano, Rhodes)、石若駿さん(Drums, Percussion)のメンバーに加えて、スペシャル・ゲストとして石橋英子さん(Vocal, Flute, Electonics)も岡山・神戸・四日市と東京の公演に参加されたツアーでしたが、いかがでしたか?
そうですね……。いきなりちょっと暗い話で申し訳ないんですけど、ツアーの前に人間関係がゴタゴタしてしまいまして、もうこのメンバーではバンドはやらないと思います(笑)。詳細は伏せますが、このことがツアー開始の2週間前ぐらいにわかったんですよ。「もう絶交だ!」とか言い合うほどの熱さでぶつかりあえるなんて逆にカッコよすぎるな、と僕は思ったんですけど。
――そんなことが舞台裏では起きていたんですね。もうあの編成でのライブが観られないのは残念な気もしますが……。
でも、ツアーの内容自体はすごく良かったですし、ファイナルの東京公演がいままで演奏したライブの中でもベストのパフォーマンスができたので、悔いはまったくないんですけどね。同じフォーマットで続けていてもできることは似通ってきてしまうので、このままダラダラと続けるよりも、ピークで終えられてよかったんじゃないかといまは思ってます。
――松丸さんは先ほどの石橋さんやジム・オルークさん、山本達久さん、大友良英さん、浦上想起さん、岡田拓郎さん、Dos Monosなどジャンルを問わずさまざまなアーティストと共演していますが、今年一緒にプレイした中で特に印象に残った人は誰ですか?
最近だと、betcover!!とのライブがとても楽しかったです。以前からbetcover!!の柳瀬くんとはデュオでやってたんですけど、8月の終わりに名古屋で初めてバンド形態で一緒に演奏しました。betcover!!はバンドとしての一体感がすごいし、メンバーはみんなすごく誠実に音楽をやっている気がします。“いやらしさ”が全然ないんですよ。音楽家として理想的なスタンスでやってるなと思いますね。
――今日は、ヒップホップグループのDos Monosのトレーナーを着てらっしゃいますね。松丸さんはサポート・メンバーとしてDos Monosに参加していて、以前はSMTK(松丸が参加するバンド)で共演もしていました。
そうですね。Dos Monosと演奏するのは刺激的です。楽器を演奏しない、トラックをつくってラップをするという形式と、彼ら自身に特有の価値観があるので、それを吸収したいなと思って一緒にやってます。これは去年の話になっちゃいますけど、Black MidiのツアーでDos Monosと一緒にヨーロッパを回ったのも経験としてデカかったです。clipping.(LAのヒップホップ・グループ)のキュレーション枠で、オランダの「Le Guess Who?」ってフェスに出たんですけど、独創的な音楽家が沢山出演していました。来場者がとにかく多くて街が一体となってフェスを盛り上げていてヨーロッパのシーンの熱量を感じました。
――松丸さんは現在、日本を拠点に活動してらっしゃいますが、そもそも幼少期からパプアニューギニアで過ごされて、アメリカのバークリー音楽大学を卒業。2018年に日本に帰国した当初は、2〜3年程度しか滞在するつもりはなかったと伺いました。実際、松丸さんの音楽からは、いわゆる日本的な文脈はあまり感じられない気がします。
小さい時に何度か日本に帰ってきているんですけど、ごくごく短期間だったので、日本の文化を知識として身につけることはできても、完全に理解できることはないんだろうな、と思います。そういう意味での「多くの人の心に刺さる音楽」みたいな作品は僕には絶対につくれない。だからこそ、自分にしかできない表現をやることが大事なのかなと思っています。
――ただ同時に以前、音楽メディア『Mikiki』のインタビューで「東京のシーンにはスタイルとして『これ』と明確に言えるものはないですけど(中略)もう少ししたら名前を付けられるぐらいスタイルとして濃い音楽が生まれてくるんじゃないかと勝手に感じています」とお話しされています。そして、その名前のついていないなにかは、「即興音楽」と呼ばれているシーンの中で生まれつつあるんじゃないかともおっしゃっていました。松丸さん自身も即興演奏の活動をしていますが、日本というローカルなシーンに新しい音楽の可能性を見出しているという、この一連の発言が非常に興味深いと思ったんです。
名前がついていないものの方が、可能性を秘めていると思うんです。そのわけのわからないものをわかりやすい形にパッケージングしたものがつくられることもありますが、そのアプローチからは真新しいスタイルが生まれてくる場所はないと思う。だから、これから完全に新しいスタイルというか、ジャンルとしてある程度の聴衆に認識されるような音楽というのは、いまアンダーグラウンドのどこかで誰かがつくっている、名前もついていない音楽なのではと思います。
――その「誰か」って、どんな人たちなんでしょうね?
これまでの音楽の歴史を振り返ってみても、なにかしらの葛藤や矛盾と向き合っている人たちが、常に新しい音楽を生み出してきたと思うんです。だからそういう人たちがつくっていくんじゃないかな……。でも、誰なのかは全然わからないです(笑)。僕も限られたエリアしか見えていないので、周りにいる人達かもしれないし、まったく接点のないもっと下の世代の人達かもしれないですね。
---fadeinPager---
「緊張」を思い出させてくれた、俳優業への挑戦

――音楽活動以外にも、今年は俳優として映画『白鍵と黒鍵の間に』出演されました。主演の池松壮亮さん演じるピアニスト「博」のサックス奏者の友人「K助」役を演じられています。サックスの演奏はもちろんですが、演技も驚くほどナチュラルで素晴らしかったです。
そう言っていただけるのは嬉しい反面、僕はいまだに恥ずかしくて直視できていなくて。ちゃんと観れるようになるまでは、もう少し時間がかかりそうです(笑)
―― 今回、映画に出演してみようと思われたのはなぜですか?
日本に来てから、やったことのないことばかりやっているので、俳優業に挑戦したのもその一つなのかなという感覚です。自分の魂を売るような仕事はさすがに断ってますが、なるべく挑戦はしてみたいと常日頃から思っています。あとは、監督をはじめとした多くの人がチームとしてつくり上げる「映画」という表現に、興味があったというのは大きいです。
――サックスを作中で演奏するというのは、普段の音楽活動とは異なるものでしたか?
今回の映画の場合は「こう吹いてほしい」というリクエストを元に演奏しているので、100%自分自身の表現としてはやっていないんです。でも、演奏として良いと思っているものは短い内容にも滲み出てしまうとは思うので、監督と話していくうちに、目指す役と素の自分の中間にある演奏になったと思います。
――映画、そして演技というものに挑戦してみて、ご自身の創作活動に返ってくるものはありましたか?
普段音楽をやっていて、緊張するってことがなくなっちゃったんですよ。どんなステージやレコーディングでも「まあ、どうにかなるか」みたいな感覚が常にあって(笑)。それって音楽家としてはあんまりいいことではない気がしていて。でも、映画の現場ではめちゃくちゃ緊張したんですよね。その感覚と向き合わされたことが自分にとってとても良かったと思います。
――先日、松丸さんがよく共演されている石橋英子さんが『ドライブ・マイ・カー』の濱口竜介監督と共同企画し、音楽を担当した映画『悪は存在しない』がベネチア国際映画祭で銀獅子賞を受賞しました。松丸さんは映画音楽に興味はありますか?
良い機会があれば必ずやってみたいと思っています。でも、僕は映画をそんなに観てきていないので、まず色々観て勉強する事が大事かなと。石橋さんは本当に映画に詳しくて、たくさん観てらっしゃるので。ただ映像に音をつければいい、ということではないと思うんですよね。映画を一緒につくるという感覚で音楽もつくるのが理想だと思うので、そういう意味でも勉強が必要だなと。
――俳優業は今後も続けていきたいと思いますか? 音楽に関係のない役もオファーがきそうな気がしますが。
いやー、それはちょっと困りますね(笑)。ジム・ジャームッシュの映画にはジョン・ルーリーというサックス奏者が俳優としてよく出てるんですよ。彼の場合はサックスを吹かない役もやってるんですけど、それは本人の素質や監督との関係値で成り立っていた気がするんです。同じように僕に信頼を置いてくださった冨永監督とご一緒できたことは幸せな経験でしたが、僕の場合、楽器を吹かない役はなかなかできないと思います。そんなことやってる前に音楽を頑張れってなっちゃうと思うので(笑)。いまの段階では人生で一度きりの面白い体験ができたな……という気持ちですね。
---fadeinPager---
無機質な地点からアプローチすることで生まれるもの

――松丸さんはサックスをメインの楽器として使用されるプレイヤー・作曲家として知られていますが、たとえばジャズなど、特定のジャンルに縛られることなく活動をしてらっしゃるようにお見受けします。特に松丸さんのソロ作や即興演奏からは、なにかを描こうとしているのではなく、鳴らしている音に対して、それ以上でもそれ以下でもない表現を突き詰めてらっしゃるように思うのですが。
そのように聴いてくださり、ありがとうございます。ジャンルの枠組みでエンターテインメントとして創作物をつくる場合は、具体的に参照できる内容を入れることによって、聴く側に一発で理解してもらうきっかけをつくる必要がある。でも、僕の作品のように特定のターゲットするリスナーがいるわけではなくても、メンバーそれぞれの創作に対する姿勢がある程度同じ方向を向いている場合、「その作品以外に存在しない表現」をメンバーと一緒に探って、構築することを最優先できるんだと思います。
――特にインストゥルメンタルの音楽だと、風景や詩的なレトリックで評されることが多くありますが、松丸さんの作品はそうした語りの方法が無意味な作品に思えるんです。松丸さんは、どのような着想点から楽曲や作品を作るのでしょうか?
僕の場合は無機質なコンセプトから入ることが多くて、風景とか感情から作品をつくることは少ないです。イメージできる物を起点にすると、自分の感情や記憶に対して曲をつくることになるので、個人的な体験にリンクする、過去に聴いてきた音楽と近しいものになりやすい気がするんです。レファレンスできる物が僕は経験としても知識としても少ないので、この方法で自分にとって未知な物を探ることを大切にしています。
――例えば“喪失”というテーマを起点とすると、喪失の体験や感情と結びつく音楽が想起されてしまい、それをなぞることになると。
そうですね。もっと無機質な地点からアプローチすれば、聴く人にとって、表現する言葉が見つからなかったり、感情といえるのかもわからないなにかを想起させる音楽になり得ると思うんです。解釈の幅が広がることにも繋がるというか。でもそれは、ガチガチの音楽理論からつくるとかそういうこととは違って……最初の話に戻りますが、つくり方に対する考え方がこの方法では大事だと思うんです。
――ソロ作は、2020年11月に1stアルバム『Nothing Unspoken Under the Sun』、22年10月に『The Moon, Its Recollections Abstracted』を発表されています。この2作品のコンセプトはどのように設定したんですか?
一言にまとめるのが難しいんですが、1stは、「言葉を発する」という行為についての表現をさまざまな角度から突き詰めました。2ndアルバムはその逆で、音楽によって生まれてくる言葉にフォーカスを当てました。1stと2ndのコンセプトは対照的でありながら、どこか共通点があるものを想定しました。
――2ndアルバムを1stアルバムと比較すると、どのような音楽的な変化があったと思いますか?
前作に比べるともう少しジャズっぽく聞こえない作品になったかなと(笑)。そもそも僕は別にジャズをやりたいわけじゃないんですよ。ピアノ、ドラム、ベース、サックスというジャズのコンボではポピュラーな編成なので、音の感触としてそういうふうに聞こえてしまうんだと思うんですけど……自分としてはジャズの文脈に直結しないようなフレーズを吹きたい、楽曲をつくりたいとは思っていて。2ndアルバムではそれに近づけたのかなとは思いますね。
――「ジャズはあまり知らない」と以前、別のインタビューでおっしゃってましたね。松丸さんは幅広いフィールドで活躍されていますし、作品もいわゆるジャズ的な音で構成されているものではない。なので、僕はジャズ・ミュージシャンとしてはあまり認識していなかったです。
そうですね、ジャズといわれるジャンル・文脈の音楽家たちは本当に素晴らしい人たちが沢山いますし、常に勉強になりますが、その文脈をパーソナルな物として感じていないので、自分自身がその文脈に乗っかってやることに対してあまりしっくりこないんですよね。
――なるほど。
育った環境的にもいろんな音楽を手当たり次第に聞けるような環境じゃなかったので、大ヒットしたヒップ・ホップの曲とかR&Bしか聞いてこなかったんです。聴いてこなかったということも含めて、ジャズは自分のアイデンティティを形成するほど特別大切なものではないってことなんだと思います。
---fadeinPager---
自分のつくりたいものと、商業的なプロダクトとの違い

――プライベートでは、この1年で大きな変化はありましたか?
引っ越しをして、防音室を買いました。東京で管楽器を演奏するのは住環境的に本当に難しいなって最近特に思いますね。制限があるからこそ生まれる独自の都会の音楽のようなものもあるとは思うんですけど、サックスをやり始めたころにいまと同じ環境だったら、僕は続けてなかったと思いますね。
――海外の場合、住環境にゆとりがあったり、公共のスペースが解放されていたり、なによりも人々の楽器演奏に対する心理的な距離感が日本とは違うなと思いますね。
「海外」と一括りで語るのは難しいですが、僕の場合はパプアニューギニアの中学・高校に通っていたころ、特に最後の3年間は多い時は一日10時間ぐらい練習していました。でも、広大な土地と周りに住んでいた人達が寛容だったお陰で、気にする必要がなかった。あとは、演奏をしている時に見える景色っていうのも大事だったと思います。いつも窓の外を見ながら練習していたんですけど、僕の住んでいたところは山の上の方にあったので、かなり遠くの別の山の峰まで見えるんですよね。いつもそこに目がけて音を鳴らすようなイメージだったり、見える景色を軸に練習していました。楽器を始めたてのころって、特にそういうイメージと音が直結するというような経験が大事な気がします。
――先ほど「新しくなにかが生まれてくるのは商業目的の音楽からではない」とおっしゃっていましたが、ご自身のつくる音楽との明確な違いってなにかあると思いますか?
「楽曲がどう捉えられるか」「売る必要がある」ということに重きをおいている、「プロダクトとしての音楽」はそこでの面白さもありつつ、とても限定的な物にならざるを得ないと思います。自分が作品を作る段階でそういう制限は気持ち的にもかけないということを前提としているのがいちばんの違いだと思います。実際に新しいものが生まれるか分からないですが、でき上がってからその後のことを考えたいので。
――つまり、芸術家として自分自身の創造性のビジョンがあり、到達したい地点があると。その場合になぜ「聴衆」を必要とするんだと松丸さんは思いますか?
芸術活動をしながらも、収入を得ないと生きていけないっていうのがあるとして、音楽としての成立という意味においては、ちょっと口幅ったいですけど、音楽は一人のためだけにあるものじゃなくて、人と人とが繋がるためのものだと思うので、リスナーが必要なんじゃないですかね……って言ってて恥ずかしくなっちゃいますけど(笑)
――でも、本当にその通りですよね。パプアニューギニアの山々を眺めながら練習していた時と、いま、作品をつくって披露するという行為の明確な違いというのは介在する人、リスナーの存在なわけで。
人がいなかったら普通の練習ですね。聴く人がいてこそ、鳴っている音に金銭に代えられない“価値”が与えられると思うので。無料でも人がいたらやるし、逆にお金だけ渡されて、そこに誰も聴く人がいなかったらそのような価値は生まれないと思います。
――人がいて、音楽を聴いてなにかを思ったり、感じるからこそ音楽を奏でる意味がある、と。
そういえば、日本に来て半年ぐらいのころに、下北沢の小さな箱でドラマーと僕の二人で即興演奏をやったんですけど。お客さんがスタートの時間には一人もいなかったんですよ(笑)。でも、お店のマスターがいたんで「とりあえずやるか」って演奏を始めたんです。1時間ぐらい演奏をしてたら、一人お客さんが来て。だから、音を鳴らしてれば、誰か聴いてくれる人は現れるんだと思います。