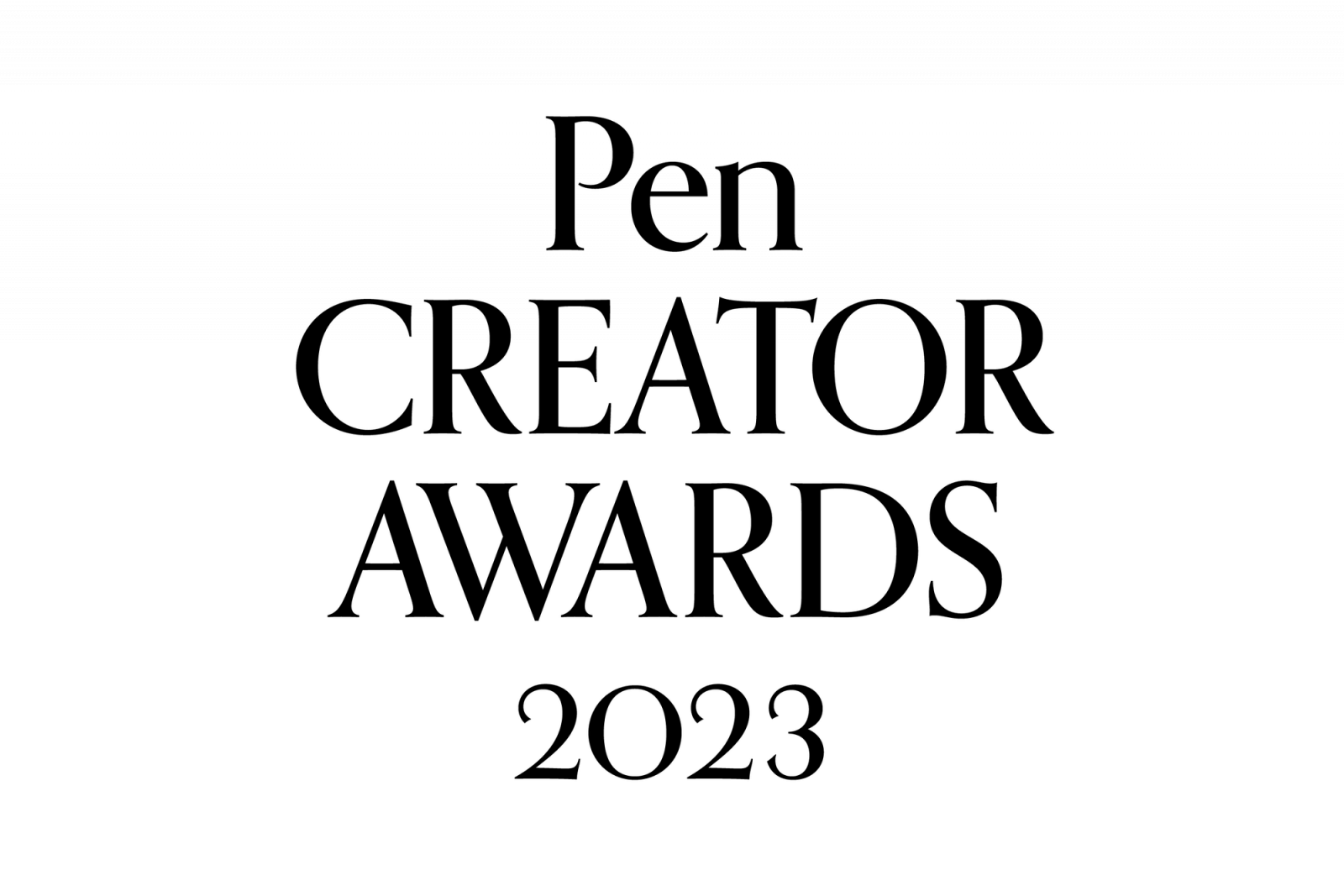2023年5月、「偉くなるためのハック」をテーマに放送が開始され、全6回を予定していながら3回で放送が打ち切りとなり、その後YouTubeで検証番組を配信、視聴者を困惑させたテレビ東京の番組『SIX HACK』。この番組を手がけたのが、2021年放送の『Aマッソのがんばれ奥様ッソ』や22年放送の『このテープもってないですか?』を担当したテレビ東京の大森時生だ。
いずれの番組もフェイクドキュメンタリーと呼ばれる手法を基に、フィクションでありながらドキュメンタリーのような質感をもち、虚構と現実の境界を曖昧にする。
1995年生まれの大森がテレビ東京に入社したのは2019年。入社後4年目を迎えた22年に「テレビ東京若手映像グランプリ」で優勝し、いまやその活躍はテレビにとどまらず、お笑いコンビAマッソの単独公演『滑稽』のプロデュースや、キタニタツヤのミュージックビデオなどを手がけている。
テレビ局員の枠を超え、多岐にわたる活動を続ける大森が2023年に手がけた作品を振り返りつつ、その作家性に迫る。

BREAKING by Pen CREATOR AWARDS 2023
確かな才能で存在感を強める、いま注目すべきクリエイターをいち早く紹介。アート、食、ファッションなど、各界のシーンで異彩を放つ彼らのクリエイションと、そのバックボーンに迫る。
---fadeinPager---
Pick Up Work

SIX HACK
2023年5月から放送されたテレビ番組。「現代社会に求められること、それは『偉くなる』こと。偉くなるためのハックを、あなたにお伝えします」をコンセプトに、「会議で勝って偉くなる方法」や「SNS勝って偉くなる方法」を紹介。全6回にわたって放送される予定だったが、3回目の放送後に休止が発表され、視聴者の間でSNSを中心にさまざまな憶測・考察が飛び交った。後日、YouTubeでその顛末をめぐる「検証番組」が配信される。配信と放送、SNSを横断し、放送休止までも織り込んだ斬新な仕掛けが大きな話題となった。YouTubeで全話配信中。
---fadeinPager---
「笑い」が内包する加害性と向き合った

1995年生まれ、東京都生まれ。一橋大学卒業後、2019年にテレビ東京へ入社。2021年放送の『Aマッソのがんばれ奥様ッソ』でプロデューサーを担当し、2022年に『Raiken Nippon Hair』で「テレビ東京若手映像グランプリ」で優勝。『島崎和歌子の悩みにカンパイ』『このテープもってないですか?』『SIX HACK』などの番組を制作。2023年にはAマッソのライブイベント『滑稽』で企画・演出を手がける。11月18日に行われたテレビ東京60周年記念式典「祓除」(配信中)の制作に携わる。
――このインタビューでは、主に2023年に手がけた仕事について振り返ろうと思いますが、まずは『このテープもってないですか?』が2022年12月27日・28日・29日に三夜連続で放送されました。
『このテープもってないですか?』は、放送がBSテレ東だったこともあり、オンエアで視聴した人はほとんどいなくて、多くの人がTVerで観ていたので、いろんな反響が届いたのは2023年になってからでしたね。
――番組概要には「今や保存されていない貴重な番組録画テープを視聴者から募集・発掘する」「当時の貴重映像をそっくりそのままお届け」と書かれていましたが、ネット上ではさまざまな憶測や考察が飛び交いました。
同じような枠で2021年の12月30日に放送した『Aマッソのがんばれ奥様ッソ!』は、正直けっこうウケるだろうなとは思っていたんです。明るいテイストの中に不気味な要素があって、視聴者が考察して謎を見つけるという、2000年代にフジテレビで放送していた『放送禁止』とかの流れにある、いわゆるフェイク・ドキュメンタリーというジャンルです。このジャンルは根強いファンがずっといるのですが、最近はあまり見なくなっていたので、そこに届くだろうと予想していました。
一方『このテープもってないですか?』は、構成に作家の梨さんに入っていただいたり、僕の個人的な趣味性が強く出ている番組で、観た人の生理に訴えるような、わりとコア向けのつくりだったんです。
でも結果、TVerの視聴数や反響の広がりは『このテープもってないですか?』のほうが大きくて、スウィングしてみるもんだなって思いました。
――2023年2月と3月には、Aマッソの単独ライブ『滑稽』で、劇場公演のプロデューサーを務めました。
僕は学生時代から演劇やお笑い芸人さんのライブに通っていたタイプではないので、劇場の公演というだけで新鮮でした。最初にAマッソの加納さんからお話をいただいた時点から、幕間映像の一部を担当するとかではなく、全体を通してのおもしろさを一緒に考えてほしいということだったんです。Aマッソ、とくに加納さんは、いわゆる芸人さんとは違う思考を持っていて、出口が「笑い」でなくてもいい、という考えなんです。どんなジャンルであれ、広義の「おもしろい」を追求している。
――その座組のなかで、大森さんとしてはどういうものを目指したのですか。
「笑う」という行為の加害性は意識しました。なんの加害性もなく、シンプルな笑いもありますが、そうではない笑いも確実にある。たとえば、深刻な問題があったときに、笑うことで無効化とは言わないまでも、笑いには深刻さを軽減するような作用があると思うんです。一方で、虐げられている人が、笑われることによってその被害を表明しづらくなったりもする。プロのお笑い芸人さんが披露するネタやトークとは別に、笑いにはそういう一面があります。僕がお笑いライブを任されたのであれば、そうした笑いが内包する加害性と、きちんと向き合いたいなと思いました。
――お笑い芸人というのは非常に特殊な立場で、一般社会のルールとは別の倫理があるというか……。
芸人さんは、基本的には誰もが「笑わせる」という目的を達成するために存在すると考えると、ある種の不気味さを感じますよね。演劇でも映画でも、喜怒哀楽いろんな感情を呼びこすためにつくられていますが、お笑いだけは「笑い」に特化している。お笑いライブというのは、観客全員が笑うためにひとつの場所に集まっているわけで、そういう意味では神秘的で、宗教的なものを感じます。
――笑わせることが職業として成立しているのも不思議な話です。
お笑い芸人という言葉自体、ハードルの上げ方としてすごいですよね。

---fadeinPager---
偉くなるためのハックは、ある種のホラーでもある
――5月と6月に放送された『SIX HACK』は、突然番組公式Xで打ち切りが発表され、代わりにYouTubeで「SIX HACKがなぜあのようなかたちになったのか」という検証番組が配信されました。あれは一体……?

ご想像にお任せします。放送と配信の融合について、局的にも個人的にもさまざまな知見をためているところです。
――そうですか。わかりました。では話題をかえて。『SIX HACK』のテーマである「偉くなるためのハック」というアイデアはどこから?
テレビに限らず、メディアの多くは、言い方や伝え方はそれぞれぞれですが、結局は「偉くなれ」ということを発信していると思うんですよ。お金を稼ぐ方法とかモテる方法とか、個別にテーマは設定されていたとしても、大きくは「偉くなれ」と。そこから着想を得ました。
――「ハック」のほうについては?
テクニックやノウハウって、揶揄されることのほうが多いですが、実際に偉くなるためには重要だと思うんです。本質的には無為なことが、偉くなるためには必須という、その虚しさも込みで番組にしてみたかった。それと、偉くなるためには、プレゼンや上司と話すときに、声のトーンやテンション、タイミングや話す順番のほうが、むしろ内容よりも大事だったりしますが、それ自体かなり不気味ですし、ある種のホラーだなって。
――そういったメタ視点で制作された『SIX HACK』ですが、観る人によっては、真正面から「役に立つハック」だと思ってしまう人もいるかもしれない。
番組内ではツッコミを入れたりもしていないので、危うさをもっている番組ではありますね。そういう意味でも、番組で紹介した「裏のテクニックを教えましょう」「ここだけの話」的なノリは、陰謀論にもつながるなと思いました。
たとえば、一般の感覚からするとものすごく変なことをしているカルトな団体がいたとして、世間の人たちはそれを見て無邪気に笑ったりするけれど、そこで笑いながら真似をすることと、実際にその団体の中に取り込まれてしまうことの境界って、ものすごく曖昧ですよね。『SIX HACK』では、そういう境界を描きたかったんです。
---fadeinPager---
従来のテレビは、デザインを軽視されていることがある

――7月には「隅田川花火大会2023 SIDE B」裏配信を担当されました。大島依提亜デザイン、Franz K Endoディレクションで、まさかテレビ東京の伝統である隅田川花火大会の中継で、あんな映像に出会えるとは。
#佐久間酒井SIDEB
— 大森時生 (@tokio____omori) July 29, 2023
オープニング
directed by Franz K Endo pic.twitter.com/GXpO4HLIZU
テレビの場合、デザインが軽視されていることがあるというか、いいデザインやかっこいい映像であることが、視聴率や配信の視聴数に反映されない感覚が個人的にはあって、でもせっかく自分が担当するからには、かっこいいほうがいいだろうと。
――そして8月にはYouTube Music Weekendの企画で、ソロアーティスト・キタニタツヤのミュージックビデオと特別番組を演出・プロデュースされました。
キタニタツヤさんは東大卒で、20代でアニメ『呪術廻戦』のオープニングテーマを手がけたりと、外からは順風満帆に見えますよね(第74回NHK紅白歌合戦への出場が内定)。でも人間誰しもそうだと思いますが、周りから見えない鬱屈と向き合っている一面があると思います。キタニさん本人ともお話をしていくなかで、完璧なキタニタツヤを完成させるために、裏には苦しい生活があるような、マルチバース的な世界をつくろうというアイデアになりました。それで、ディープフェイク的な手法を使って描こうと。
――モチーフや参考にした作品はあるんですか?
「素敵なしゅうまつを!」のミュージックビデオに関しては、ちょうど映画『aftersun/アフターサン』を観たあとで、構成の梨さんや監督の寺内康太郎さんも観ていたので、その影響はありましたね。父親が撮影した子どもの頃の映像と、回想シーンと、大人になってからの想像とがごちゃ混ぜになっているような。当時の楽しかった思い出が、大人になってから冷静に振り返ると暗い影もあるっていうのは、けっこうな衝撃だったので。
---fadeinPager---
現代の閉塞感が、"歪さ"を求めている
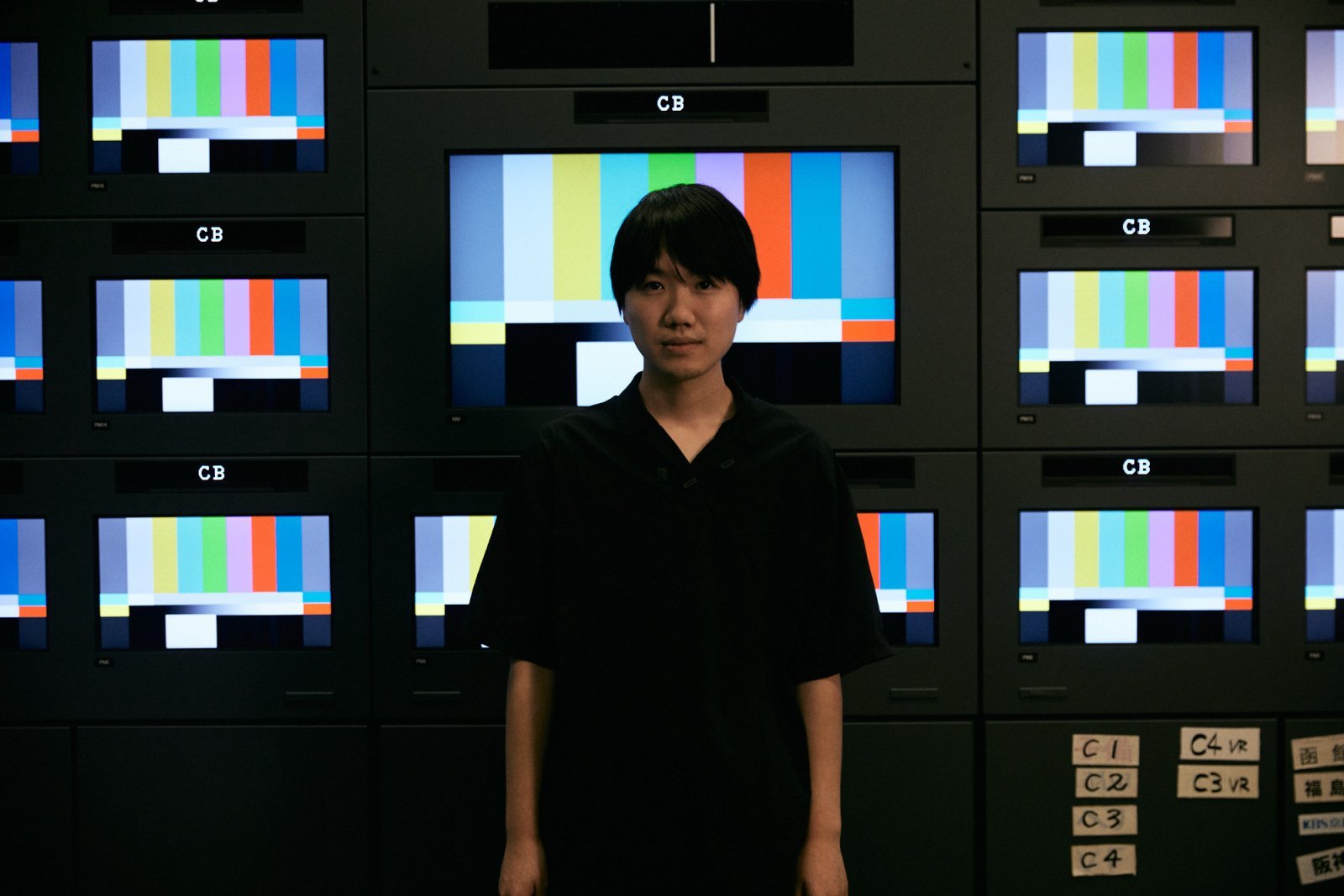
――このところホラー作品が注目を集め、ネット上では『近畿地方のある場所について』がバズったりと、かなり盛り上がっていますよね。
ここ数年は異常な盛り上がりだと思います。とくに『近畿地方のある場所について』は、わかりやすい怖い話とは違って、ホラー小説の『忌録』にも通じるような、不穏なピースがたくさんちりばめられていて、読んでいる人の内部から不気味さを生み出してくタイプの怖さがあります。こういう作品は難易度が高いので、ホラー好き上級者にはハマるけど、一昔前ならそこまでバズったりしなかった気がしますが。
――現代にホラーが流行るのは、どうしてだと思いますか?
「もうどうにもならない」という、閉塞感を多くの人が感じているのかもしれませんね。これはダメだなっていうときって、落ちるところまで落ちていきたいみたいな気分になるじゃないですか。その感覚に、不気味なコンテンツがハマっているような気がします。しかも最近は、音や映像の効果で怖がらせる「ジャンプスケア」という手法のホラーよりも、『フェイクドキュメンタリー「Q」』のような、読み手や視聴者が能動的に関わって、気づいたら沼にズブズブと沈んでいくタイプの怖さに需要があるように思います。
――大森さん自身は、「怖いもの」のどういうところに魅力を感じていますか?
僕は単純に怖いものというよりも、歪だったり不気味なものが好きなんですよね。音楽ジャンルでいうとヴェイパーウェイヴとか。自分の世代だと、たとえば『ポケットモンスター 金・銀』をみんなやっていて、BGMも楽しい思い出として刷り込まれているんですけど、それがヴェイパーウェイヴになると、スクリュードされて、耳障りなノイズ音も入って、あの頃の楽しかった思い出が歪まされていく。その雰囲気が好きで、それでしか得られない栄養があるんです。
――その感覚はテレビとも相性がいいでしょうね。テレビは大衆の象徴であり、ノスタルジーを喚起させやすいので、歪ませるには格好の題材。
あの時代、みんなが観ていた『めちゃ×2イケてるッ!』とかは、モチーフとして強いですよね。アメリカだと、ペプシやフォードを歪ませるヴェイパーウェイヴが一部の若者の間で熱狂を生んでいるんです。強かった頃のアメリカのイメージと結びついて、それが今は崩壊していくような感覚に若者たちが共鳴している。モチーフは違えど、日本人にもその感覚は当然あるので、いまという時代に対する期待の持てなさが、怖いものや歪なものへと向かわせるのかなと思います。
日本のヴェイパーウェイヴだと、ジャスコとか屋上遊園地がモチーフになることが多いのですが、そういうささやかな日常の幸せのほうが、記憶のノスタルジーと結びつきやすい。それこそ『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ! オトナ帝国の逆襲』に描かれていたようなモチーフが歪んでいくことに快感があるというか。
――心霊スポットとかには興味ないのですか?
ないんですよ。僕はあくまでフィクションが好きなので。
これからは、もっと穏やかな気持ちで仕事がしたい
――今年は「FORBES JAPAN 30 UNDER 30 2023 世界を変える30歳未満」にも選出されました。
選ばれたこと自体も光栄ですが、これをきっかけに企画が通りやすくなったらいいですね。これまではできなかった予算のかかる企画とか。あとは、メタ的なものをずっとつくり続けてきたので、そこを突き詰める意味でも、ドラマだったり映画だったり、フィクションを本腰入れてつくれたらいいなと思ってます。
これまで一緒に仕事をさせてもらってきた映画監督の寺内康太郎や酒井善三さん、ダ・ヴィンチ・恐山さん、梨さん、Franz K Endoさん、みなさん世界で通用する才能を持っていると僕は思っているので、そういう方たちと何か大きな作品をつくりたいです。
――2024年に向けて、何か考えていることはありますか。
具体的な企画というよりも、気持ちの問題なんですが。僕はずっと、自分のつくったものに対して「これおもしろくないかも」という強迫観念が強くあるんです。でも、これからはもっとおおらかな気持ちでやりたい。作家寿命を延ばすという意味でも、強迫観念に苛まれてやるよりも、穏やかに仕事したほうがいいかなと。